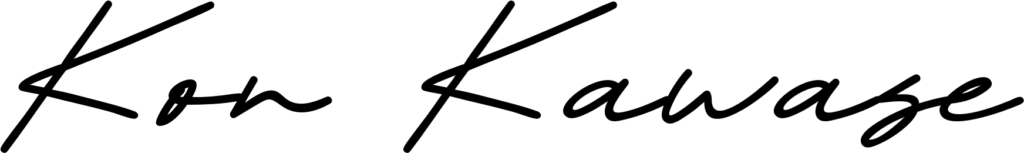幼いころ、体調不良で学校に行けなかった。母は世間体を気にした。ある朝、目が覚めると、彼女は包丁を持って私のベッドの横に座っていた。「先に死んで。追いかけるから」 私は「そっか」と思って納屋に行き、太い釘を手首に刺した。意識が戻ったとき、彼女は周りの人に「この子が勝手にやった」と言った。毒を盛られる気がして、手料理は食べなくなった。
都会の偏差値の高い大学と、大きな会社に入ること。それはしばしば否定されるが、田舎の危ない環境にいる子どもからすると、逃亡を正当化してくれる希望の光だ。入ったあとにどうなるかなんてどうでもいい。手に入るらしい幸せ、お金、名誉、権力、安泰、人脈も、身近な例がなくて憧れるに至らない。知らん。とにもかくにも生命維持だ。
私は脱出した。寂しさや辛さやどうしようもなさ、ひねくれた性格を、「あの人のせいで」という言葉と結びつけないようにした。言葉はうまく使わないと呪いになる。私は私だけで存在したかった。私が主演のドラマに、彼女はいかなる端役でも登場してはいけない。仕出し弁当屋に扮して現場に紛れ込むのもだめだ。
そうやってしばらく生きていたのに、結婚後、突然あの日の記憶がYouTubeの広告のように生活に押し入ってきた。私はいい妻になれるだろうか。家庭を作れるだろうか。溜め込んだぐちゃぐちゃの感情で、夫を傷つけないだろうか。
病院に行き、薬を飲んだ。長い時間が過ぎた。プログラムを組みなおし、新しい私を起動した。バグを見つけるたびに、夫と話し合い、修正してきた。穏やかな生活のなかで、大学院に行きたかった気持ちを思い出した。逃避の手段にすることなく、学問に向き合いたい。
なぜ文学を学ぶのか。入学試験の面接で聞かれそうなことを、いつも頭の片隅に置いて勉強している。
人文学の究極目的のひとつは、暴力の否定である。あるいは暴力を肯定するなんらかのロジックなりナラティブなりを批判することである。たとえば人文学の一領域である文学研究なら、その末端で推敲される作品を面白く鋭くアカデミックに読むという行為は、たとえば―あくまでたとえば―こうした究極の目的のひとつに奉仕するのでなくてはならない。
阿部幸大『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』、p.138
自分に内在する暴力の可能性を忘れずにいたい。そのうえで、暴力に暴力で応戦することなく進む力を身につけたい。
自分の人生に集中できるように、嫌な感情を引き起こす広告で途切れさせないように、プレミアムプランを作ろう。お金はかからない。設定を、考えかたをぽちっと変えるだけ。言葉はうまく使うと物事を終わらせられる。言い切ってしまうと、過去として、現在から離せる。今なら言えるぞ。
さよなら。