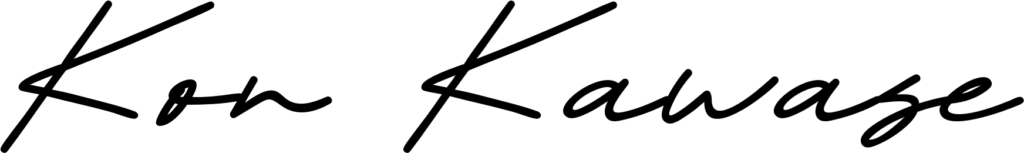大学2年生のとき、インターン先の広告会社が倒産した。広告業界の人たちは、自分たちのことを広告代理店と言わない。広告会社と言う。出勤日は社長に日報を書いて提出する。返信には必ず松下幸之助の言葉がついてきた。それじゃあ代理店じゃん、自分の言葉で言えよ、そんなんじゃつぶれちゃうぜ、とえらそうにぶすぶす思っていたところ、言葉は呪いなのかもしれない、ほんとうにつぶれた。負債が膨らんで、社長とその補佐役が失踪した。私を見てくれていた社員が「あの人たちはもう戻ってこれないね」と言ったから、「この業界にですか」と尋ねたら、「いや、この世界」と返ってきた。新聞に小さく記事が出た日、会社のウェブサイトにアクセスした。画像が消え、キャッシュだけが残っていた。会社の屍だった。コンサルとか広告とか、外から言葉をつかう会社じゃなくて、ものづくりをしている製造業で、中から言葉を発したいと思った。
製造業ならどこでもよかったので、どこにエントリーしていいのかわからなかった。好きなものから連想すればいいと聞いてやってみた。それはたぶん「チョコレートが好きだからお菓子業界」みたいなもののはずだったのに、私は「アルファベットが好きだからアルファベットの名前の会社がいい」という軸にして、アルファベットの名前の会社ばかり受けた。
人事の人たちは松下幸之助の言葉が好きだった。カーネギーもお気に入りだった。広報の人たちは広告宣伝費をあまりもってなくて、広告代理店を頼みにしていた。アルファベットの会社はすぐに屍になりそうな会社ではなかったけれど、つかっている言葉が上滑りしているように見えた。つるつるしていて、人との摩擦を起こさない。中は空洞になっていて浮き、滞りなく流れていく。よくも悪くも残らない。
もともとは比喩なのに、使われ過ぎて比喩としての意味をなさなくなった表現をデッドメタファーという。新しい言葉の発明ばかりだとやりとりに時間がかかってしまうから、言葉はある程度死んだほうがいい。自分がつかう言葉のどれくらいが死んでいるのかを意識しながら、たまに言葉がひょこっと動くように扱うのが好きだ。誰かの言葉の繰り返しだな、これどこかで聞いたな、その言葉とその言葉が来たということは次にあれが来ますね・・・ああやっぱりね、とか思うことなく言葉を受けとれる環境は、緊張感がありながらも心地よい。言葉に生があるとき、それをつかっている人も生きているように感じる。