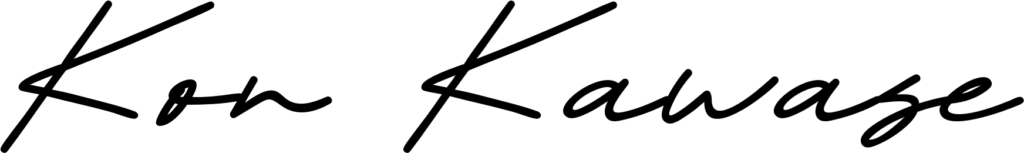Steven Millhauserの、A Haunted House Storyという短編の感想です。2024年2月26日時点で、日本語訳は出ていません。訳は私によるものです。以下、ネタバレを含みますので、受け付けない方は飛ばしてください。
ハリントン博士の家は、町で噂の心霊スポット。奥さんが突然死してからは引っ越してしまい、長いこと誰も住んでいない。奥さんは自殺したとも、殺されたとも言われている。
夏。それぞれの進路が決まった高校生の少年たち。夜、ハリントン博士の家で肝試ししてみようという話になる。率先して行ったトムは、戻って来てから話さなくなる。次に主人公が手を挙げる。
幽霊が出ると散々言われる話の流れのなか、部屋をひとつひとつ確認していく主人公は、次第にハリントン博士の家のことが好きになる。
in a house I had already come to love.
既に愛するようになった家で
Steven Millhauser, ‘A Haunted House Story’, p.125, from “Disruptions”
部屋のあちこちに残っているもの、たとえば木の机、椅子、ランプ、ふくろうの形の瓶が載った冷蔵庫、麦わら帽子、オルゴール、バイオリン、野球帽をかぶった大きなクマのぬいぐるみを見ていくうちに想像する、かつてのこの家の姿。あたたかい。楽しそう。居心地がいい。こわくない。主人公はこう言う。
this dark house awakened me, pierced me, with something I hadn’t known I longed for. It occurred to me that only once had I thought of the hanged wife. A death might have happen here, but this was no place of moans and sighs, of eerie whispers. Only people who knew joy could have lived in this house.
この暗い家は、ぼくが切望していたとは知らなかった何かでぼくを目覚めさせ、突き刺した。ぼくは一度だけ、首を吊った奥さんについて考えたことがあると気づいた。死はこの場所で起こったのかもしれないけれど、ここはうめき声やため息、不気味なささやきが響くところではなかった。喜びを知っている人だけがこの家に住むことができたんだと思う。
Steven Millhauser, ‘A Haunted House Story’, p.126, from “Disruptions”
あまり直接的には書かれていないけれど、主人公の家は冷たい。父親は仕事熱心で厳しく、滅多に書斎に入らせない。母親は存在感が薄い。ハリントン博士の家で感じた、楽しい気持ちや、穏やかな気持ちを、主人公は自分の家で感じたことがなかった。主人公とトムはおそらく同じ気持ちを抱いた。幽霊がいるとかいないとかそういうことじゃない。それを他の人と共有できないと思って、トムは黙って町を出たし、主人公も黙った。じきに新しい町で、新しい生活が始まる。ひとつずつインテリアを選び、使い、愛着をもち、人を呼んで一緒に過ごしていくなかで、自分の部屋、自分の家、自分の家族や人生をどんなふうにしていこうかと考える気がする。They will remain haunted by the question of what is peaceful or joyful.
ミルハウザーの作品は、基本的に大きなことは何も起こらない。でも、指に針をぷちっと刺すような、小さな、確かな痛みをくれる。pierceという単語は、ジーニアス英和大辞典だとひとつめの意味に「先のとがったものが人や物を刺す」とあり、ふたつめの意味に「深く感動させる、心に響く」とある。最新作のDisruptionsという短編集は、正直なところ、昔のテーマの繰り返しが多くてあまり好きじゃないのだけれど、この作品はとても響いた。