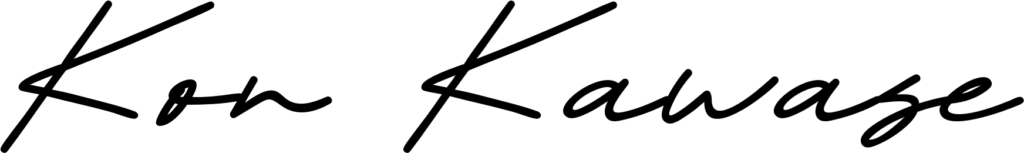文芸誌Paris Reviewのメールマガジンが、毎日詩を届けてくれる。過去に誌上に載った詩の中から、少しずつ。
夏になると思い出す詩だ。
I Was Icarus
by Ulrich BerkesIt must have been a hot summer back then, when I could fly.
I was maybe seventeen.
My room was on the ground floor, facing the back.
Night after night I lay on the bed and imagined myself flying.
That was a strain, I tell you.
Usually I’d lie perfectly still for an hour before my body rose from the bed.
Very slowly I rose, until I hovered a meter or so off the floor.
Then with swimming strokes I propelled myself through the open window.
Outside I flew higher and higher, over the garden fence, over the clothes-lines, over the roof tops and the apple-trees on the outskirts of town.
The entire flight I felt the wind’s touch on my skin,
and sometimes I heard voices, calling.—Translated by George Kane
Paris Review, Issue no. 106 (Spring 1988)
(もともとはおそらくドイツ語で、英訳をKane氏がおこなった)
日本語訳 by 紺
私が飛べたのは、きっと暑い夏だったのでしょう
たぶん17歳でした
私の部屋は1階で、家の裏側に面していました
毎晩ベッドに横たわり、自分が飛んでいるのを想像しました
それは本当に緊張することでした
ベッドから体が起き上がるまで、1時間はじっと横になっていました
ゆっくりと起き上がり、床から1メートルほど浮いた感じになりました
それから泳ぐようにして、開いた窓から飛び出しました
庭のフェンスを越え、物干しロープを越え、屋根の上を越え、町はずれのりんごの木を越え、どんどん高く飛んでいきました
飛んでいるあいだずっと、風が肌に触れるのを感じ
時々、呼ぶ声が聞こえました