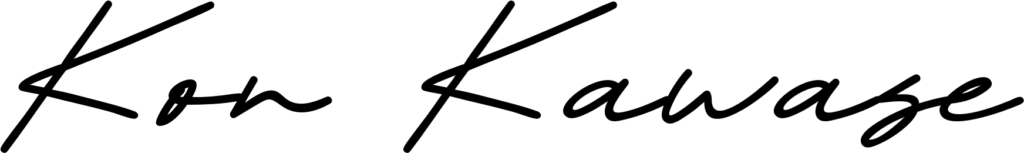何にもつよい興味をもたないことは
不幸なことだ
ただ自らの内部を
目を閉じて のぞきこんでいる。何にも興味をもたなかったきみが
ある日
ゴヤのファースト・ネームが知りたくて
隣の部屋まで駆けていた。(中略)
生きるとは
飯島耕一 「ゴヤのファースト・ネームは」から抜粋
ゴヤのファースト・ネームを
知りたいと思うことだ。
ゴヤのロス・カプリチョスや
「聾の家」を
見たいと思うことだ。
見ることを拒否する病から
一歩一歩 癒えて行く、
この感覚だ。
(何だかサフラン入りの
サフラン色した皿なんかが眼にうつって……)
その入り口に ゴヤの
ファーストネームがあった。
これは、鬱病を患っていた詩人が回復期に書いた詩。寝込んでいたところ、ふっと、「あれ、ゴヤのファースト・ネームって何だっけ?」と思う。ああ、えーっと、何だっけ、えーっと、と考えあぐねる。布団に寝ていられなくなって、隣の部屋にある本棚へ急ぐ。愛読書、あるいはめったに開かない厚い百科事典を開くなどして、ゴヤを探す。そんな情景を想像した。
元気が出ない時に現れる小さな知的好奇心は、夜空、雲のあいだから見える北極星みたいだ。ずっと待っていた。たかだか他人の名前ひとつでも、あ、知りたいと思えたことがうれしい。布団から出なきゃ出なきゃという切迫感で頭がいっぱいだったのに、気づけば体が出てしまっている。ファースト・ネームがわかったら、次は画集を見たくなる。好きな作品の描かれた年に、ゴヤは何をしていたんだっけ。この絵の、この色合いは、あれやこれやに似ているな。スペインの風景を想像し始める。私だったらパエリアが食べたくなる。世界が広がる、ふくらむ。
私の知的好奇心への欲求は、仕事で忙しくて、でも勉強したくて、という時期にはあまり切実ではなかった。頭と体は動いていて、与えられた仕事で知的好奇心っぽいものを満たせていた。内臓の病気で臥せたとき、頭も体も動かせなくて、何も考えられなくなった。読みたいものはおろか、食べたいものも取り込めない。暇つぶしの音楽にも動画にも、感覚を開けていられない。私は疲れて、諦めて、閉じていった。
時間がとても流れた。布団の中で、急に「括弧は英語で何と言うんだっけ」と思った。ベッド横のワゴンに入った電子辞書に手を伸ばす。届かなくて、起き上がる。和英辞書には、parentheses。英和辞書には、こんなことも書いてあった。「本文とは文法的関係がないが、注釈として挿入された語句」。頭の中で光が走った気がした。飯島にとってのゴヤのファースト・ネームも、私にとっての括弧も、寝てばかりの生活に、ふいに入り込んできた小さな挿入句だった。
回復の途中で少し感覚が開くようになると、世界は穏やかな隙間風のように私たちの中に入ってきて、あれやこれやとつながり、知的好奇心を刺激する。知的好奇心に促されて、体は動き、世界が広がり、ふくらむ。世界を追いかけて、私たちは駆ける。ゆっくり、おのおののスピードで。