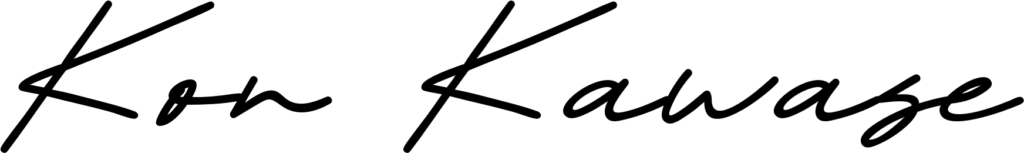New Essays Every Monday
-
言葉の森へ行く
私の書斎は、照明がオレンジ色の図書館と、いつまでも座っていられるカフェのソファ席、機動性に優れるコックピットみたいなオフィス、森林浴ができる場所をかけ合わせたイメージだ。黒、焦げ茶、緑がメインカラー。落ち着くデザインと耐久性を重視した物選び。ここで長く過ごすことになるだろうからと、独立の時にこだわって作った。耳栓をすると、タイマーが鳴るまで静かな世界。英語と日本語、どちらもうまく読み書きできる人を目指して生きている。
伝わらない言葉
1987年の春、お昼過ぎ。田舎の村に生まれた。落語の「じゅげむ」を暗記して保育園で披露したり、小学生の作文コンクールで毎年入賞したりした。テレビ局主催のコンクールで銅賞をもらった詩が、系列のラジオ局の番組で読まれた日のこと。両親と、8才の私、6才の妹、2才の弟はワゴン車に乗り、カーラジオをつけて待つ。事前に伝えられた時刻が近づいて、私は唇を噛む。女性が、うちの田んぼの四季を書いた詩をゆっくりと朗読する。私は唇を噛んだまま、つい口角を上げる。母が「紺ちゃん、すごいね!」と言う。「すごいね!」の意味は、幼いのに長文を暗記できたから。コンクールで入賞したから。じゅげむのおとがたのしかったからとか、はいしゃさんがとてもこわかったけど、なかずにがんばったらおねえさんにほめられてうれしかったとか、たんぼのいろがかわるのがきれいで、ともだちにじまんしたかったとか、彼女がそういうのに全然興味がなかったことは、幼いながらも感じとっていた。泣き叫ぶしかできなかった子が、言葉でコミュニケーションを試みるまで成長しても、両親は変わらず、毎晩ケンカして、ののしり合っていた。母は私の手を振り払って実家に帰ったり、橋から飛び降りることをほのめかしたりした。アルコール、タバコ、魚焼きグリルの臭い。
新しい国語の教科書が配られると一気に読んだ。連絡帳の「せんせいあのね」の欄には、ささいなことをたくさん書いた。小学校高学年のある日まで、もっと勉強して練習すれば、言葉をうまく伝えられるようになるんだと思っていた。夕方、帰宅すると、私の部屋がぐちゃぐちゃに荒らされている。机の引き出しはひっくり返されて、中のものが床に散乱している。カーテンと布団カバーは破れている。私が友だちとこっそり始めた交換日記の鍵を見つけられなかった母の暴挙。知りたいことを知りたがる。農家の嫁として男子を望まれる中、第1子は女子だった。そして3才で死んだ。言葉にできない大きな苦しみがあったのだとは思う。おねえちゃんが死ななければ、私が男の子だったら、なりたかった母親になれたのかもしれない。でも、うまく言えないけど、このやり方は違うよ。「まあ、いつものことだ」と片づけていたら、右手の人差し指がギクッとして、見ると血が出ていた。お年玉を貯めて初めて買った、MY LITTLE LOVERの8cmシングルCDが割れていた。心臓から流れてきた血が、指先からしずくになって落ちた。
泣かないことを 誓ったまま 時は過ぎ
痛む心に 気が付かずに 僕は一人になった中学で英語を習った時、言葉というものを初めてまじまじと見た。aとpとpとlとeの組み合わせが、apple、りんごになった。単語と単語の組み合わせが熟語や一文になって、その組み合わせが段落になり、段落がまとまると文章になった。単独ではほぼ意味をもたないアルファベットが、他と組み合わさることで意味をもち、拡張していくのがうらやましかった。そこに存在する意味があっていいなあ。担任が英語教師だったので、連絡帳の「今日のできごと」を英語で書きたいと思った。数日迷ったあとの、おそるおそるの申し出は、先生の「お!」という快諾で上書きされた。ぎゅうぎゅうに書いた私のいびつな英文に、彼が隙間を見つけて赤入れし、コメントを書いてくれたこと。母が英語を読めなかったこと。このふたつが私を守った。知的好奇心を安心・安全にふくらませる土壌になった。眠っていた種が目を覚まし、芽を出した。英単語や英文法をおぼえていくにつれ、草木が育った。
発音を褒められて、英語の弁論大会の学校代表に選ばれた。名前を呼ばれて、ステージに上がる。目の前には5人の審査員と大勢の観客。私はなめらかなボディランゲージを挟みながら、ていねいにアイコンタクトし、スピーチする。”Thank you for listening.”(ご清聴ありがとうございます)で終えると、大きな拍手が起こる。ステージから降りる。しばらくしてもう一度名前を呼ばれて、ステージに上がる。県大会で上位入賞だ。だけど、ふう、気をゆるめちゃだめだ。次は全国大会だ。―ここまでイメトレしていた14才の私は、ステージの上でスピーチを全部忘れた。何も思い出せなかった。私の可能性を信じて見守ってくれる人たちの前で、5分間、立ちつくしていた。「思い出せ、思い出せ」とすら思えない。無。静まりかえった空間に、チンとベルの音が響く。失格。原稿が飛んだタイミングで、機転を利かせて、”I love silence. Let’s close our eyes and enjoy the moment together for five minutes.”(私は静けさが好きです。目を閉じて、5分間、一緒に今という時を楽しみましょう)とでも言えばよかった。翌年、15才の挑戦は、思いを込めた原稿を時間内に話しきれず、ベルに遮られて終わった。またしても失格。日本語でも、英語でも、人にうまく伝えられない。入賞して、家族に温かく迎えられる同い年の子を遠くからじっと見ていた。私にはないものばかり。
見つけた仮説
美術部で描いた環境ポスター、「ただいま 地球が がけっぷち」が、県のコンクールで1位になった。サスペンスドラマで船越英一郎が出てきそうな崖に、手足のある「地球さん」が立っているもの。森林が行方不明というチラシをくわえた鳥が空を飛び、崖の下では波がしぶきを上げる。スピーチ原稿とキャッチコピーを何度も書き直していて気づいたことがあった。感性だけでは人に伝わらない。論理なだけでは書き手も読み手もおもしろくない。ものを書いたり作ったりするには、感性と論理の融合が大切なのでは?
高校生になると、この仮説を検証するために、いろんな文芸手段を試した。俳句はお茶のペットボトルに2回載り、あまたの作文は何かしらの賞をとり、詩は全国コンクールで9位に食い込んだ。もう一度挑戦した英語弁論は県3位。高校は、部活に入れないくらい、毎日遅くまで授業がある進学校だった。大学受験に関係ないこと、勝手にあれこれ応募して賞をとってくることに、職員室の先生たちの目は冷ややかだった。英文エッセイが全国2位との通知を読んで数日後、審査員のひとりから家に電話がかかってきた。「あなたのエッセイはすばらしかった。本当は1位だったのだが、ユニーク過ぎて2位にしなければならなかった」との謝罪。は? 1位の作品集を読んで理解した。「アメリカに行って、様々な人々に出会いました。貴重な経験でした。将来は世界中で活躍できる人になりたいです」というエッセイのほうが、たしかに1位にふさわしい。私のエッセイは、言葉の世界のおもしろさを、想像力をめいっぱい使って表現したもので、優等生的ではなかった。あくまで仮説検証だったから、何位だろうとよかった。ただ、他者からの評価は、作品の質だけでは決まらないことを知った。偉い人たちの考える枠におさまることは、結果的に起こることかもしれなくても、私が最初から目指したいものではない。伝わっても、場の目的や個人の好みにそぐわないことがある。とても気に入られることもあれば、まったく好まれない、嫌われることもある。でもそれは、自分の存在の肯定や否定には関係ない。高3の秋に訪れたこの機会は、私が何のために書くのか、何を書きたいのかを考え始めるきっかけになった。1位の人のように、私も貴重な経験をした。
慶應義塾大学を志望したのは、小論文の過去問がおもしろかったから。なんとなく、この大学は小論文の問題で生徒の感性と論理のバランスを見ているような気がした。入試で、論拠のひとつに「この前シュークリームを焼いた。いい匂いがした。オーブンの中でふくらむ様子はまるで生きているみたいだった」と書いた。高校の先生に報告したら「何を血迷った」とあきれられたけど、私は論理的に正しいと思ったし、自分の感性も表現できて満足だった。それで合格したので、やっぱりおもしろい大学だと思った。入学後、人間的、知的、経済的、立場的にすごい人たちにたくさん会い、圧倒された。まずは東京弁、上級英語、フランス語を習得し、英米文学と英語学をバランスよく学んだ。文芸をやっていると、自分の中で文学と語学が分離しない。だから、ゼミを文学にするか英語学にするか迷った。結局英語学を選んだけれど、文学をもっと学びたかった気持ちは残った。私はこの大学で、英米文学を学ぶおおまかな地図と、すごい人の学ぶ姿勢、文学の英語の難しさ、自分の意欲を知ったから、いつかまた学べると思った。中学1年でseasonを「sea+son=海の息子」と言っていた私は、卒論を英語で書いて卒業した。ちなみにインターンは広告代理店で1年、アルバイトはコーヒーチェーン。どちらも偉い人や本部に日報を褒められて、そのことで店長や同僚に嫌味を言われた。
社会でのフィールドワーク
「大学院ではなく、実際の世界で言葉がどう使われているのかを知りたい」「広告やメディア系の会社ではなく、伝えたいモノをもつ広告主の側で、言葉を研究してみたい」と考えて就活した。リーマンショックの冷たい風が、私の履歴書を何十枚も吹き飛ばした。それを拾ってくれた愛知県のメーカーに入社。人事部で、国内外の人材開発の仕事をした。経営者の言葉、製造や開発の現場はわからないことだらけだった。でも、私の「わからない」は研修を受ける人たちの最初の状態でもあることに気がついた。頭の中にはてなマークばかり浮かぶ状態を、どうすればびっくりマークに変えられるか。自分の学びの過程、気持ちの変化を記録して俯瞰し、「ここでつまずいたので○○を入れよう」「順番を変えたほうがわかりやすい」「ここは正解がひとつじゃないので気楽に意見交換できる場に」というふうに研修体験を設計した。工場と販売会社が海外メインの会社だったから、研修の設計者、講師、ワークショップのファシリテーターとしてアジアを飛びまわった。
研修を研修会社に外注するのが基本の環境で、そもそもから考えて作ろうとするのは浮く。何かを変えようとする時には反発がある。1日3万歩くらい工場を歩きまわって現場・現物・現実を確認したり、担当者に話を聴いていたりした頃、トップ層から「あいつは我が物顔で歩いてる」と吹聴された。熟練の技術者は「お嬢ちゃんに何ができる」と笑ったけれど、「何も知らないので教えてください」と伝えたら、こだわりや工夫をていねいに教えてくれた。海外工場のライン工は、新入社員の私よりも若い女性が多かった。彼女たちはわずかな休憩時間、消灯したフロアのラインの横で、洗面器を裏返したような椅子に脚を開いて座り、黙々とスマホを触っていた。中国の工場で、銭単位のレベルでコストを抑える人たちの取り組みを見たあと、香港のビルの最上階のバーで、販社の人が接待費で高価なワインを開けるところに同席した。ギャップに吐きそうになった。輝く照明の光や談笑の音が消え、モノクロの無声映画を観ているようだった。何にも手をつけずに先にホテルに戻り、備え付けのジャスミンの臭いのボディーソープで体を強く洗った。私へのパワハラを主導した上司は、マレーシアに出向になってから価値観を変え、私に謝ってくれた。至らない点があった私も謝った。そのあと、出向先で突然亡くなった。反日感情が強まった時期の入国審査の冷たさも、国際女性デーだからとプレゼントされた花束の甘い香りも、取引先の工場でクレープのようにさっと薄く焼かれた部品のできたての熱も覚えている。店頭に並ぶ製品の姿からは見えないものたち。混沌、不条理、無力感、割り切れなさの中でも、いつも観察し、耳をすませ、メモをとっていた。私は会社にあるもの、たとえばメール、プレゼン、会議、現場の様子、財務諸表、KPI、エクセルデータ、報告書、ビジネス本、論文などを通してずっと、社会や人々の物語に触れている感覚でいた。自分の考えに研修やプレゼンという形を与えるのは、ものを書くことに似ていた。人に届いて何かを動かす、あるいは何かを解決するような、できるだけ意味のある言葉を世界に存在させようと努めていた。
水曜日と金曜日は定時帰宅の日。部内へのリマインダーメールの担当になった。前任者からの引継ぎで、同じ文面を自動配信すればいいと言われた。リマインダーが必要なのは、定時帰宅していない人が多いからだった。コピペ自動配信で効果出てないじゃん。あ! 社内の昇格要件にTOEICのスコアが必要になったはず。「定時に帰って英語を勉強しませんかメール」に変えちゃお。期待されてない雑務は、目的を外さなければ勝手に変えても怒られない。私が集めてきた、おもしろい英語表現、語源、和製英語などを、飽きずに2年間紹介し続けた。送信したそばから感想が届いた。「ベア(賃金アップのこと)は、bearじゃなくてbase upの略です」と送った日、離れた席の労務グループの人たちが、「bearだと思ってた!」と盛り上がっていたように。定時帰宅率が上がったのは、たぶんみなさん英語を勉強したくなったからだと思う。
4つ年上の、かっこよくてユーモラスなエンジニアの同期と結婚した。彼は「紺ちゃんと会社の同期として出会うための時間調整」として、2浪していた。その期間、彼は背伸びしてがつがつ勉強していたわけではない。浪人1年目は図書館に通って、センター試験に関係ない、ネットワーク技術の勉強をしていたらしい。2年目にそろそろセンター試験の勉強をする気になって、ぼちぼち予備校に通った。もともとの性格もあるし、いつも同級生より2歳上であることも関係していると思う、彼は悠然だ。言葉足らずな彼と、言葉が好きな私のあいだには、うんざりするくらい、たくさんのすれ違いと言い争いがあった。彼の中には、私のことを好きな気持ちと、嫌いな気持ちが強く共存した時期もあったと思う。今ならわかる、言葉はコミュニケーションのすべてではない。感情的な言葉のやりとりになりそうな時、彼は黙って部屋にこもる。私が母に似てしまうんじゃないかと泣く時、昔のことを思い出してしまう時、彼は何も言わずに私を抱きしめて、クレヨンしんちゃんに出てくるグリグリ攻撃のやさしいバージョンで、こめかみをマッサージして緊張をほぐしてくれる。私が疲れている時、ねぎらいの言葉の代わりに、お高めのアイスクリームを買ってきてこっそり冷凍庫に入れておいてくれる。周りに流されず自分のことに集中し、成果を出し、頼もしく、憎たらしいくらい余裕がある一方で、彼にも弱さや脆さや辛さがある。それさえ言葉にしないから、私は彼の存在やエネルギーに目を配るようになった。言葉で元気になる人ではないので、私も黙ったり、お弁当や夕飯を好物にしたり、不意にぎゅーっと強く抱きしめたりと工夫している。世界は大きく、人間は深い。言葉はその中のほんの少しに過ぎない。言葉で表現できないことがあること。表現手段が言葉ではない人たちがいること。沈黙の中にも豊かな対話があること。言葉にならない思いをすくいとろうとすること。無意識の言葉の使用に、加害性が伴いうること。私はこれを彼との生活を通して学んでいった。
人材開発でスペシャリストになるキャリアが当時の社内になく、商品企画部に異動した。オンラインコンテンツの企画と多言語対応。エンジニアやデザイナー、外部クリエイターと働くうちに、私も言葉の領域を深めたいと思うようになった。外部のスタジオで、写真撮影に立ち会って動きまわった日の夜。帰りの車の後部座席に、社内トップデザイナーと座った。いつも口数が少ない彼女は、回転寿司屋の看板を見ながら、「あなたはいわゆるデザイナーじゃないけど、やってきたこと、やってることはデザインだよ」とつぶやいた。キャリアの行き詰まりが溶けて、デザイン会社に転職した。言葉周りをすべて任せてもらえたので、肩書きがよくわからない。クライアントへのインタビューと現場の観察、調査、専門知識の勉強で、デザインの方向性や核になるものを言葉にした。会社を表すスローガン。商品のネーミング。リーフレットやウェブサイトのキャッチコピーと説明文章。オウンドメディアの記事の企画、取材、執筆。SNSの運用。いろいろ書いた。
夢と書斎とカリキュラム
組織の中にいた期間の収穫は、自分の言語感覚が仕事につながるとわかったこと。退職してのんびり過ごしていたら、内臓疾患で思うように動けなくなり、想定外に長く休んだ。社会システムの中で学んだことの整理や探究をしたり、学びを手放したりした。積ん読の山も登った。そして元気に個人事業主として独立。インタビュー、コンサルティング、リサーチ、サービスデザイン、ライティングなどの仕事。
2022年、ペンネームのウェブサイト、Twitterアカウント、毎週エッセイを書いて発表する習慣を作った。英米文学をもっと学びたかった記憶を取り出して、文学の英語をもっと読むための勉強を始めた。家庭教師に教わるうちに、読解力と知的好奇心が増し、大学院進学を目指した時期もあったけれど、結局やめた。愛知県の大学は、文学よりもコミュニケーションのための英語を重視する印象がある。英米文学を学べる場所や教員は減少傾向にあり、あったとしてもカリキュラムが物足りなかったり、大学院に学生が何年も入学していなかったりする。私の目的は学歴ではないから、他の土地に引っ越してまで進学したいわけじゃない。
私の夢は、この先の人生に、当たり前に英語と日本語の読み書きがあるようにすること。もっと深く読めるようになりたいし、世界を感受する耳や目や心を豊かにしたいし、自分で書く文章の幅も広げて書き続けていたい。その過程で、新しい自分を知りたい。自分のテーマを見つけたい。私と夫が80才くらいの時、夫はコンピュータに熱中し、私は文学と創作に熱中し、できるだけ健やかに、笑い合って、助け合って生きている日々があるといい。
英語でも日本語でも深く読み書きできる人に近づくために、2025年の8月から9月にかけて、カリキュラムと勉強環境、人間関係を作った。柱は4つある。
① 某大学Aに、学部研修生として秋入学した。これは大学の既卒者が、特定の科目について、特定の指導教官のもとで研修する制度。一般的には院進の準備のために使われる制度だけど、この大学の研修料は比較的手ごろで、何年も学び続けている人がいる。私は、イギリスの大学の博士号をもったネイティブの先生のもとで、英文学の勉強をしている。自分の専門分野の需要が縮小傾向にあることを自覚したうえで、戦略、柔軟性、ユーモア、反骨精神をもって教壇に立ち続ける人。細やかな気配りをする人。私は勧められた授業と、半期につき4回の面談を通して、半年で1本のレポートを書く。定期試験がないので、試験のための勉強をしなくていい。自律的な学びを支援してくれる環境。
② 某大学Bを退官した英米文学の教授の、演習授業のような読書会に参加している。英語の短編を読む。当番は資料を準備して発表する。某大学Aには精読の演習が少ないので、その補強。月1回だけど、アーカイブがたっぷりあって、無料なのがうれしい。先生は著名な人なのに、偉そうにしない。参加者の素朴な疑問や意見に耳を傾ける人。「たくさん失敗して大丈夫です」と参加者を励ます人。作品の好きなところを楽しそうに話す人。
③ 国内外の大学のシラバスなどを参考にして作ったリーディングリストをもとに、文学作品を楽しんだり、勉強したりしている。必要に応じて、大学の図書館を活用したり、先生たちに質問したりしている。
④ 頭と体を鍛えている。英語の4技能はネイティブレベル(CEFRのC2)まで伸ばしたい。ウォーキングと筋トレもできるだけやっている。頭を使いすぎて体が動かないことがあり、逆もしかりなので、いいバランスを見つけて強くありたい。
某大学Aの先生には、私の夢とカリキュラムを伝えてある。 応援してくださる。独学の魅力は、ひとりの時間を十分にもてること。自分でカリキュラムを作ったり、修正したり、逸脱したりできること。独学の限界は、他者の目とフィードバックが得られないこと。だからこの環境は理想的だ。正規の大学院よりもカリキュラムが充実していて、学費がうんと抑えられ、自分の夢に結びついている気がする。
とはいえ、何が「よい読み手」で「よい書き手」なのかはわからない。これから学び、試行錯誤し、変化していくうえで、考えていくべき問いだ。
言葉が好きという気持ちを持ち続けながら、自分の仮説を検証していたら、いつの間にか、社会で戦うための武器として言葉の力を研いでいた。直接的で実用的、説明的な言葉を駆使する一方で、内心ずっと、そういう言葉をつかう歩みを止めて、黙りたかった。今、私の書斎で、言葉は武器ではなく、呼吸、光、日々の営みそのものだ。静かな言葉の森に入って、私と言葉の関係を築きなおしている。それは、安全な場所に逃げ込むことではない。森の奥では幽霊が出る。大きな嵐も来る。老いと病も避けられない。それでも私は読む。書く。迷いながら先へ進む。より静かで、より根源的な形で、社会と深く関わりたい。
私の言葉が、沈黙が、あなたの世界に少しでも届いたらうれしい。
-
キャンパスの探検
ラッシュアワーが苦手だから、東京にいたときは、早く起きるか大学の近くに住むかしていた。会社員時代も会社の近場に住んでいた。私は今月から大学生で、今期は1限の授業を取っている。夫と暮らしているので、あまりに早く寝るのも早く起きるのもよくない。朝早くにごそごそ音がするのは嫌だろうし。
事務手続きを済ませるついでに、前もって通学のシミュレーションをしてみることにした。9時過ぎからの1限に、余裕をもって間に合うようにしたい。早すぎず、遅すぎず。いいぐあいの時間を探す。
7時半に家を出てバス停に向かう。横断歩道で待っている間に、目の前をバスが通過した。あちゃー。時刻表を見ると、次のバスはすぐ来るようだった。さっきのバスは2分遅れ。思っていたより渋滞していない。よし。スピッツの「楓」を聴こうと音楽プレイヤーをいじっていたらバスが来た。時間がゆっくり過ぎるようで、意外とせわしない。
8時過ぎの地下鉄は日中よりも混んでいたけれど、東京のラッシュアワーに比べたらかわいい。私の通学ルートに関しては、ぎゅうぎゅうにならない。人と人のあいだにじゅうぶんな空間がある。乗る駅と降りる駅の開くドアが同じで、地味にうれしい。名古屋には、エスカレーターを立ち止まって利用しなければならないという条例がある。調査によると、条例施行後に立ち止まって乗る人が増え、2024年度は90%を超えたらしい。そうは言ってもラッシュアワー。なんだかんだで歩いちゃうんでしょ。と思っていたら、みなさん静かに2列で乗っていた。それなりに利用者の多い駅なのに。名古屋は何もない、とよく言われるけれど、こういうところは住みやすい。
駅を出て、大学まで歩く。緑の木々が多くて、森の中を歩いているみたいだ。夏は永遠の長さに感じた道も、涼しくなれば短く思える。心地よいとは言えないまでも、ストレスのない通学エクスペリエンスで、森へ行く。2回目の大学生なので、この機会がいかにありがたいかを噛みしめる。
学生証をもらい、入学手続きでお世話になった教務の方にお礼を言い、健康診断結果のコピーを提出し、授業が行われる予定の教室を確認する。どれも建物が別々なので、キャンパスを歩き回る。1限に駆け込む学生たち、教科書販売に並ぶ学生たちとすれ違う。私は彼らを若いなあと思うから、きっと彼らは私を若くないと思うはず。だけど一緒の空間で学ぶ。不思議だ。
ぴかぴかの学生証をぴっとかざして図書館に入った。岩波文庫が揃っている棚ににやける。学部の編成で縮小した分野の本もたくさんある。最新の本も定期的に入っていそう。空気の悪いところ、いいところ、自習スペース、コピー機、エレベーター、お手洗い、避難経路を確認する。居心地がよくて気に入った。
帰り道。ちょうど2限が始まる前の時間帯。右手にスマホ、左手に日傘を持って下を向きながら歩いている学生たちが、狭い道いっぱいに広がっていた。それがたいへん長い列をなしている。そういえば、通学路にはいたるところにマナー喚起のプレートが出ていた。こういうことね。ここは片側を空けるべきところよ。道を譲ってもくれない人たちの波を、息を止めてすばやく逆行した。ようやく抜けたところで、息を吐き、秋風を吸い込んだ。これからここでがんばるんだ。
-
DREAM
英語で初めてフィクションを書いた。乗っていた海賊船が難破して、無人島に辿り着いたピーターが、仲間のトッドを見つける話。
8月末からクリエイティブライティング(創作)のオンラインレッスンを受けている。先生はイギリス人の女性で、出版経験のある作家、ジャーナリスト、クリエイティブライティングの講師。オランダで法律とジャーナリズムの学士号を取り、南アフリカでジャーナリストとして活躍したあと、クリエイティブライティングの修士号を取り、現在はジャーナリストから英語教師に転向しようとしている途中の方。
オンラインの先生探しは難しい。プロフィールに「あなたに合ったカリキュラムを作ります」と書いてあっても実際は違ったり、事前のメッセージを全然確認しなかったり、遅刻ばかりだったり、Wi-Fi環境が不安定でフリーズしがちだったり。適当に話していればレッスン時間が過ぎてお金が入ると思ってるように見える、気の抜けた人もいる。過去には私が「年齢にしては若く見えすぎる」「絶対大学卒業してない18才でしょう」と爆笑されたりもした。
私は、高校を出たあとの学びは、自分が自分の目標に対して学びのプロセスをデザインする、そのためにある部分を先生に協力してもらうという姿勢が必要だと思っている。オンラインの先生探しはそれが特に重要な気がする。「きっとこちらのことを思って丁寧に教えてくれるだろう」と受け身で期待していると、ただ時間とお金とエネルギーを使うだけで何も残らない。
8月、期待せずに探した。プロフィールを見ただけで、この人はよさそう、この人は違う、なんてジャッジしていくのはおこがましいことだけど続けた。私が探すのを諦めれば、傷ついた気持ちに対して「それでも」と言わなければ、新しい先生には出会えない。
勝手に書類選考して、どなたのトライアルを受けようかなと悩む。そうしていると、ある先生2人からメッセージが届いた。彼らのプロフィールページにアクセスして、私が何かのアンケートに答えたことで、私が興味を持っていることを知ったらしい。一方のメールは事務的だった。もう一方は、プロフィールでも感じていた、「この方、自分の言葉を話す人みたい」という印象を強めた。
メッセージを返した。こういう計画を持っていて、○○の部分を助けてくれる先生を探している。私のバックグラウンドは××で、語学力はこれくらい、など。この「計画」が試金石だ。他の人は出さないものだと思う。それに対して、事務的に軽く返すか、自分の言葉で返すか。
彼女は「少し待っててください」と送ってきた。そしてそのあと、私のメッセージへの感想、背景への共感、「とてもおもしろそうな計画」「ぜひ手伝いたい。やり方はいろいろあると思うから、話して試行錯誤してみましょう」といった長文が届いた。
トライアルの時間は日本時間の14時からにした。イギリスは朝6時だ。早すぎない? でも彼女が枠を開けてるんだし。そう思いながら会ってみた。ミーティングルームに入る前に、冷たい水をたくさん飲んだ。
「南アフリカの刑務所を取材してたとき、朝6時にキックボクシングやってたのよ。だから5時起きの習慣になってる」と言った。ジャーナリズムの限界と、クリエイティブライティングの講師への転身の理由、今後のキャリアプランを教えてくれた。「私は困難を抱えている人々の話を聴いて、それをまとめて、お金をもらう。でもそれでその人たちにお金が入るわけじゃない。私はその人たちが、自分の物語を自分で表現できるような仕事をしたいの」
自然と安心できる空気を作れて、かつ深い話を交換できる人との出会いは宝物だ。
日本ではあまりクリエイティブライティングの教育がされていない。幼少期から受けている国の人たちがうらやましい。だからまずはキッズ用の教材でやってみようということになった。画面に、海賊の帽子をかぶった男の子が肩に緑のオウムを乗せ、「じゃーん」とでも言いたげに立っている絵が現れた。周りには海、砂浜、木々。その場で名前をつけた。どういう性格か、なぜここにいるのか、どんどんでっちあげた。「そのあとは?」と聞かれて、えっと、そうですね、死にますと言ったら、「話が終わるのでだめ」と笑いながら叱られた。先生の英語は聞き取れるし、私も話せる。失敗しても大丈夫。えっちらおっちら漕いでいく。
「というわけで、今日作った話を書いてきてね」と言って、トドロフのプロットの理論(Todorov’s narrative theory of equilibrium)を教わった。まず平和な状態があり、崩壊が起き、その崩壊を認識したうえで、修復し、新しい平和な状態に至る。授業は録画されていて、ダウンロードして繰り返し観ることができる。作品を書いて、次の授業の3日前までに先生に提出する。てっきりレッスン内でフィードバックを受けるのかと思ったら、「授業5分前までには返す」と言っていた。それはあなたの時間を奪うことにならない?と聞いたら、「私はこういうやり方が好き。だから気にしないで」と言った。
書き始めてすぐ、創作していくと、小説を深く読めるようになる気がした。1作目なんだけど、まだ3センテンスしか書いてなかったけど思った。
理論に従ってプロットを組み、細かいところを詰めていく。英語以前に、「なぜ男の子が海賊に憧れるのか」「海賊とは何か」「生き残らせるために妥当な漂流日数と必要なものは何か」「海賊船を新しく作るにはどれくらいの時間がかかるのか」「ピーターのペットのオウムを使わなきゃいけないけどどうやって」などに悩み、調べながら書いた。キッズ用の、プロットを学ぶ課題にどこまでリアリティが求められるのかわからないけれど、納得しないと書けなかった。マンガの『ワンピース』を読んでおけばよかったと思った。荒々しい波を切って走る大きな海賊船とは対照的に、私の小さな舟はたいへんにのんびり進んだ。
ある日の夕方、クライマックスを書き始めたら止まらなくなった。買い物に行く予定だったのに、それどころじゃない。物語がそこに来ているので応対しないといけない。夫にLINEしたらパエリアのデリバリーを頼んでくれた。大きな海鮮パエリアを見て、「海賊がどんちゃん騒ぎするときってどんな感じだろう」と思った。私はできたてほやほやのピーターとトッドの話をして、夫はリアリティについて突っ込んだ。ベイビーライターには優しくしてくれと、命乞いした。
ノートに書いた草稿をパソコンに打ち込んで、プリントアウトし、文法や文章の飛躍を中心に何度も推敲したあと、書き始めてすぐの直感が確信に変わった。精一杯書いたから、自分の限界がとてもわかる。もっと書けそうだし、読めそうだ。
私の英語のフィクションの最初の読者は絶対彼がいい。原稿をメールで送ると、しばらくして私の部屋に来て感想を教えてくれた。日本語訳も渡しておいたけど、「英語のほうがいい」と言っていた。そうなの、英語のほうがいいよね。なんか英語だと書けるものがあるんだよ。キャラクターの名前のバリエーションがないと相談したら、「全部スタートレックから取ればよろしい」とのことだった。なので、次の主人公はピカード。ということは、フランス生まれの、ホットアールグレイティーが好きな人になる。えー。
ピーターを見つけたとき、トッドは「夢じゃない」と言った。私も先生との出会いに「夢じゃない。やっと見つけた」と言いたい。いい関係を築きたい。明日の授業を楽しみにしている。