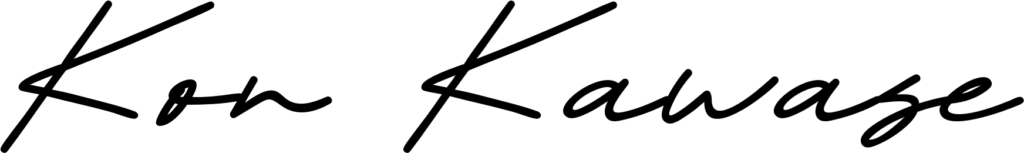New Essays Every Monday
-
夢のわたあめ
8月1日から慌ただしくなり、9日にその浮遊感をつぶやき、今日は25日、現在進行形でこの状態が続いている。新しい場所、新しい人、英語の会話とメール。
変化の中では、ハビットトラッカーが役に立たなくなる。どんな習慣を選び直すのか、構成し直すのかを、動きながら考えている状況だ。ひとまず励んでいるのは体調維持と体力づくり。
ひとつひとつのことに、できるだけ期待しないようにしているから、感情的な疲れはない。空いた時間にネイルサロンに行ったり、花を生けたり、新発売のパックを試したり、レシピを見ないで適当な料理を作ったり。これは気晴らしというより、夢をふくらませる空気入れだ。まず夢みたいなことが楽しいので、そこに余暇の楽しさが加わると、ふわふわをふわっふわにしてしまう。ふんわりぐるんぐるんの大きなわたあめみたい。つまんで食べたそばから、すぐに新しいわたあめが巻きつく。
お風呂あがりに油断すると、どこで寝落ちするかわからない。眠りが浅くて、明け方に夢を見る。朝起きて目をこすっても、まだふわふわのわたあめの中にいる。
-
探しものは何ですか?
探しものは何ですか?
見つけにくいものですか?
カバンの中も つくえの中も
探したけれど見つからないのにまだまだ探す気ですか?
井上陽水「夢の中へ」
それより僕と踊りませんか?
夢の中へ 夢の中へ
行ってみたいと思いませんか?この曲は「うふっふ~ うふっふ~」と続く。高校の化学の先生が、「いいよな、『うふっふ~』って歌ってりゃ金が入るんだから」とよく笑いながら言っていた。
大学の英文学史のノートが途中で切れていた。ロマン主義以降ぜんぶ。必修だから欠席したはずがない。どこ行った。
今年はこれからロマン主義以降の勉強をやりなおす。教科書のアンソロジーも十分に説明が詳しいんだけど、それをサブにしてご自身の見立てや重要だと思っているところを伝えてくださった先生の言葉も読み返したい。
大学の資料は全部残してある。教科書、ノート、ルーズリーフ、配布されたプリント、フィードバックつきのレポート、卒論、履修案内、シラバス。ルーズリーフとレポートのバインダーを引っ張り出してきて探す。さくさくやればすぐ終わるのに、さくさくやれない。「ああそういえばこういう勉強もしたな」と思ったり、B+のレポートを読んで何がAに至らなかったのかが今ならわかって悔しがったり、「この作家の別の作品、つい最近読んだ」とうれしくなったり。私には写真のアルバムや日記帳を読み返して懐かしむ習慣がない。大学の資料を保管しておいて時折読み返すのは、似た気持ちなんだろうか。
頭の中で井上陽水がずっと歌っていた。
休む事も許されず
笑う事は止められて
はいつくばって はいつくばって
いったい何を探しているのか休むことが許されて、笑うことも止められない場所で、紙をめくりながら、英文学史Ⅱのノートの残りを探しているんですよ。
探すのをやめた時
見つかる事もよくある話で
踊りましょう 夢の中へ
行ってみたいと思いませんか?これからどうやって生きて行けばいいんでしょう、生きる意味ってなんでしょう。お金が厳しいので留年は無理。絶対ストレートで卒業して就職。そんなことで頭がいっぱいだった当時の私の愛読書は、小説だと主人公が逃避する話ばかりで、哲学だと困難に立ち向かうことを説く文章ばかりでした。探しても、探すのをやめても、探しものは見つかりませんでした。
探しものは何ですか?
まだまだ探す気ですか?
夢の中へ 夢の中へ
行ってみたいと思いませんか?たくさん走って、こけて、また走ってはこけました。今はいろいろなことを了解して、切り落として、選択して、時には妥協もしてここにいるんですが、当時の私からしたら、夢のような場所で、なりたかった自分に近づいている気がしますよ。心身も、生活も、人間関係も、少しずつ、周りの人の助けも借りながら作ってきました。
英文学演習IVのルーズリーフのあいだに、英文学史Ⅱのルーズリーフが4枚と、プリント3枚が挟まっていた。0.3のシャープペンでびっしり書かれた文字から浮かび上がる当時の私に笑う。どうしてこれだけルーズリーフにしたの。未来の自分への思いやりが足りないじゃん。
見つからないなら作る。これが、今の私が見つけたものです。踊るなら夫と一緒がいいです。新しいノートも作ります。自分の道を進みますね。
うふっふ~。

-
Humanity 101 人文学入門
アメリカ現代詩の翻訳。
humanityは、「人間であること」、「人間性」、「人間らしさ」などを表す単語。複数形のHumanitiesは、人間の文化や歴史、価値観、信条などを研究する学問「人文学」という意味で、哲学、史学、文学、語学などを総括する。101は授業の「入門レベル」を意味する。
– – – – – – – – – – –
人文学入門
作:デニス・デュアメル
訳:川瀬紺私は慈善家か、大統領か、少なくとも世の中の物事に関心をもつ人になる道を歩んでいたけど、慣習に従わない学生だったから、たくさんの遅れを取り戻さなきゃいけなかった。だから人文学入門を受講した(独立した学部の人文学科とは違うやつ)。期末試験に落ちたとき、教授は私に、それまで学んでこなかった基礎を学ぶため、人文学の補講を受けるよう勧めた。彼女が言うには、私は従来の方法にそぐわない学生だったかもしれないが、人間としては伝統から外れない人とのことだった。それはまるで、あなたの顔と心が10倍の拡大鏡の中で輝いているかのように、教授が時々親密なことを言うときの感じだった。
それで私は人文学補習を受講した。簡単にAが取れるように聞こえるけど、信じてほしい、実際はかなり大変だった。類推問題が出された。たとえば、パリス・ヒルトンが裕福なアメリカ郊外の子どもにとってどんな存在であるかは、アメリカの中流階級の子どもが (1) アメリカの貧困層の子ども、(2) 冷蔵庫に何も入っていない家の子ども、(3) 冷蔵庫がまったくない第3世界の子どもにとってどんな存在であるかと同じである、みたいな。戦争の原因についてエッセイを書く課題があった。それは現象だったのか。人間の低レベルな動物的本性だったのか。経済的なものだったのか。心理的、性的、宗教的(善vs悪とか)なものだったのか。建物に寄りかかってうずくまっているホームレスの人にかがんで話しかける宿題があった。必ずしもお金や食べものをあげる必要はなかったけど、「お元気ですか」「好きな色は何ですか」みたいな言葉をかけなきゃいけなかった。老人ホーム、刑務所、デイケアセンターを見学した。ベッドのそばに立ったり、知らない小さな人たちと床に座って色を塗ったりした。彼らは最初泣いて、私たちを怖がっていた。私は退学寸前だった。専攻を変えたくて、オフィスアワーに教授のところへ行った。彼は「心が打ち砕かれているからですか」と尋ねた。彼は、私が毎日1時間、イヤホンで大音量の音楽を聞いたり、テレビの前に座り込んで現実逃避すればうまくやり遂げられると考えていた。私は、「でもそれが問題なんです。今の私は、コメディ番組をつけても、ポップソングを聞いても、ビールのCMを見ても、どこにいたって、人間のことを想像してしまうんです」と言った。彼はドアを閉めて、シャツの下にある刺し傷の跡を見せてくれた。そして、見えていてもいなくても、誰もがこういう傷をもっていると想定しなければいけないと言った。
彼は、時間が経てば本当に楽になる、音階を奏でる方法を学んでいるうちは音楽を作るのは難しいと言って、私を安心させてくれた。自分の可能性に気づかせてくれた。私の人間らしさを確信させ、いつか博士号を取れるかもしれないと思わせてくれた。だけどまずは、追加の単位を取るために、デタッチメントについての論文を書かなきゃいけなかった。
Humanity 101
Denise DuhamelI was on my way to becoming a philanthropist,
or the president, or at least someone who gave a shit,
but I was a nontraditional student
with a lot of catching up to do. I enrolled in Humanity 101
(not to be confused with the Humanities,
a whole separate department). When I flunked
the final exam, my professor suggested
I take Remedial Humanity where I’d learn the basics
that I’d missed so far. I may have been a nontraditional student,
but I was a traditional person, she said, the way a professor
can say intimate things sometimes, as though
your face and soul are aglow in one of those
magnified (10x) makeup mirrors.So I took Remedial Humanity, which sounds like an easy A,
but, believe me, it was actually quite challenging.
There were analogy questions, such as:
Paris Hilton is to a rich U.S. suburban kid
as a U.S. middle-class kid is to:
1.) a U.S. poverty-stricken kid,
2.) a U.S. kid with nothing in the fridge,
or
3.) a Third World kid with no fridge at all.
We were required to write essays about the cause of war—
Was it a phenomenon? Was it our lower animal selves?
Was it economics? Was it psychological/sexual/religious
(good vs. evil and all that stuff)? For homework
we had to bend down to talk to a homeless person
slouched against a building. We didn’t necessarily have to
give them money or food, but we had to say something like
How are you? or What is your favorite color?
We took field trips to nursing homes, prisons,
day-care centers. We stood near bedsides
or sat on the floor to color with strange little people
who cried and were afraid of us at first.
I almost dropped out. I went to see the professor
during his office hours because I wanted to change my major.
He asked, “Is that because your heart is being smashed?”
He thought I should stick it out, that I could make it,
if I just escaped for an hour a day blasting music
into my earbuds or slumping in front of the TV.
I said, “But that’s just it. Now I see humanity everywhere,
even on sitcoms, even in pop songs,
even in beer commercials.” He closed his door
and showed me the scars under his shirt
where he had been stabbed. He said I had to assume
everyone had such a wound, whether I could see it or not.He assured me that it really did get easier in time,
from The Norton Introduction to Literature, Shorter 13th edition, pp. 797-798
and that it was hard to make music when you were still
learning how to play the scales. He made me see
my potential. He convinced me of my own humanity,
that one day I might even be able to get a PhD. But first
I had to, for extra credit, write a treatise on detachment.