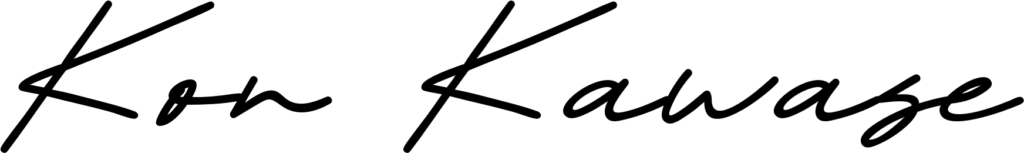9月6日(水)
手術の日。医療従事者のチームワークはすごい。私が手術台に横たわる傍らで、声を掛け合い、てきぱき仕事をしていく。私はひとりで考えたり調べたりする空間と時間が多めに必要で、かつ人とのコミュニケーションの時間はひとりの時間と切り離したいタイプなので、彼らのようには働けないなと感嘆していた。オペは寝ている間に終わった。麻酔が抜けるまで気持ち悪かった。吐き気が強いし、体が痛くて眠れないしでたいへんだった。
9月12日(火)
経過が悪いところがあって再手術。前回は緊張しっぱなしだったのに、2回目は落ち着いていた。唯一、麻酔が切れたときのことを心配していたけど、短時間、麻酔量少なめですんだので平気だった。
9月13日(水)
医師が、今度の経過は順調に見えると話していて少し安心した。太い緊張の糸がぶちっと切れて泣いた。看護師に処置されることに慣れてきた。
9月14日(木)
医師が、経過が順調だと話してくれて心の底から安心した。
9月16日(土)
医療用ホチキスを取ってもらった。残りは、再手術分の抜糸だけ。数日先でも、先のことを考えると待ちくたびれるので、毎日その日の、目の前にあることにだけ集中して、感謝するようにしている。
9月17日(日)
スープストックトーキョーで買っておいた冷凍カレーを夫と食べる。夫は東京チキンカレー、私はえびのフレンチカレー。「おうちスープストックだ!」と言って楽しんだ。
事実列挙の文章は好きじゃなくて、それを経てどう思ったかとか、何を連想したかを中心に書きたいのだけど、このところそのスイッチがオフになっていてうまくいかない。冷静に、落ち着いて、無感情でいようとする感じ。時間に「淡々と過ぎていってください」と思いつつ、心のだいぶ奥のほうで、「つまらん」とふてくされている。