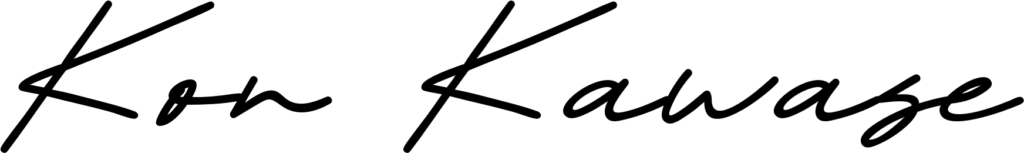New Essays Every Monday
更新情報が届くニュースレターはこちら
-
未来になって今日が幻になるまで
夫が風邪をひいた。治りかけで会社に行ったら調子を崩すことの繰り返しで、ぽつぽつと会社を休んだ。薬を飲んでよく寝ていた。元気がない。
数日して、「何食べたい?」と尋ねた。「からあげ」と返ってきた。「病人にしては食欲ありますね」と言ったら、目をそらして笑っていた。いいことですよ。特別に、お好みのものばかり食卓に出した。
ある日、彼は私が勉強しているところにたたたっとやって来て、膝をつき、私に抱きついた。膝のブランケットに顔をうずめる。猫の「ごめん寝」みたいな体勢。顔が上がる。目に光が戻っている。
彼はそのまま、食べたいものの話をしていたと思う。私は黙って光にみとれていて、聞いてなかった。この光がいかに大切か、どうすれば守れるか考えていた。時間は過ぎ去るというシェイクスピアのソネットが頭に流れて、いつかこの眼も、そこに映るものとしての私も消えるんだと思った。大切にしてもなくなってしまう。悲観しても楽観しても、消える未来はなくならない。
少し遠くまで出かけすぎたと気がついて、彼のくせ毛の髪を両手でわしゃわしゃとかき乱した。
今日 君が笑う それだけで春だ
メレンゲ「春に君を思う」
ありがとう ありえないよな
未来になって今日が 幻になるまで
笑われるくらいに 笑ってて欲しい -
生活と勉強と創作
生活が何よりも大事だなって思います。人生をかけて仕事をするのではなく、私は人生をかけて生活をして、それを仕事に落とし込みたいという気持ちがあって。だから、生活してどんなことを感じるか、大事にしたい。
杉咲花 NHKスイッチインタビュー2025年度の入試日程はまだ発表されていない。おそらく例年どおりだろうから、このごろは直近のそれに合わせて勉強している。体が強い弱いの話ではないけれど、薬を飲んでいるので、その影響が変に強く出ることもあるし、ショックな出来事があれば落ち込み、がんばりすぎて疲れることもあるしで、穏やかで平坦な日々ではない。
この先の人生に、生活に、当たり前に英語の読み書きがあるようにしたい。英語・日本語ともに、もっと深く読めるようになりたいし、世界を感受する耳や目や心を豊かにしたいし、自分で書く文章の幅も広げて、書き続けていたい。夫はコンピュータに熱中し、私は文学に熱中し、できるだけ健やかに、笑い合って、助け合って生きる、という夢。これはふたりとも80歳くらいのときのイメージ。
「大学院を目指そう」と決めてちょうど1年が経ち、違う自分になった。「何のために大学院に行きたいのか」や、「その先」を意識することが増えて、ありたい自分でいられるように、送りたい生活を送れるように軌道修正してきた感じがする。お酒やお菓子、外食をやめて、本や貯金にまわすようになった。どうせ治らないと諦めていた睡眠障害を完治させようと、生活が数週間単位で不安定になることを覚悟していろんな薬を試し、合うものを見つけ、うまく眠れるようになった。運動量も増えた。
夢に対して必要なことが各種能力のレベルアップや読書で、それがうまいこと入試や大学院の過程でクリアすべきハードルになっているのだけど、今のところ、今日のところ、なんかまだ独学で行きたいな、行けるなと思う。試験に合わせて自分の能力を急ごしらえして、攻略して、「さ、さあ、次…(息切れ)」の学生生活を全然したくない。
専門的な研究活動はしたいのだけど、そこに至るまでに、お金や時間の心配なしに、自分でやっておきたいことがある。それがたとえ入試や大学院の授業で求められるレベル以上のものであっても、あるいは余計なものがあっても、私の夢には必要なのだ。道中に大学院があるだけで、大学院のために勉強しているのではない。そして勉強のために生きているのでもない。まず夫との生活があって、その中に勉強と創作がある。
夫と食べて寝て起きて暮らす生活の中に勉強する自分がいて、そこで得たものから何か新しいものを発見したり作ったりしている。仕事人間だった私は、たやすく勉強人間になる。衣食住と夫と自分のことをほったらかしにしてしまう。だから努めて、生活を何よりも大切にしたい。その基盤が、勉強や創作や、夫との関係をよりよくすると思う。
1年で学習習慣が確立した。次はもっと感じたい。自分が何を感じるのかを大切にしたい。想像や連想をやわらかくふくらませたい。苦手をつぶしていく戦略性と、作品を批判的に読む鋭さも持ち合わせたい。休むときはしっかり休んで、夫との時間も充実させたい。私がずっとしんどそうにしていると、彼は自分のしんどさを表現できないだろうから(そしてそういうことがこの前あったから)、気持ちの余裕を残しておきたい。
単にできるだけ早く入学したほうがいいのかな、という理由で今年の秋受験を予定していたのだけど、見送ろうとしている。冬の受験はどうだろう。わからない。せっかく現役の学生ではないのだから、一般的なキャリアからは早々に大きく逸脱しているのだから、生活第一に生きて、自分のタイミングで受けよう。完璧主義には陥らないように、でもやりたいことをできるかぎりやって次に行けるように。
このことを夫に話した。ジャージャー麺を「うまいうまい」と食べながら、「紺ちゃんのペースでいい。『この本を何時間で読まなきゃ』より、『あ、読んでたらこんな時間』のほうが絶対いいじゃん。そういう時間もたっぷり必要」と言っていた。彼は大学受験で2浪した。未来の就職先で私と同期として出会うために、時間調整していた。夢のために私も見習う。焦らない。あきらめない。「明日はそのジャージャーソースをうどんに絡めてお弁当にするよ」と返した。
-
もうすこし、眠っててもいいですよ

私は自分が光る星だと思っていました
疑ったことはありませんでした
自分が虫だなんて知りませんでした
でも大丈夫です、私はまばゆいから私は自分が空から落ちた星だと思っていました
願いを叶えてあげる小さな星
私は自分が蛍だなんて知りませんでした
でも大丈夫です、私は輝くから私は自分が光る星だと思っていました
疑ったことはありませんでした
自分が虫だなんて知りませんでした
でも大丈夫です、私はまばゆいから韓国の音楽や本の言葉が綺麗だなあと思って数年経つ。音楽は英訳がつけば、本は翻訳が出れば理解できるから、恩恵にあずかって自分では学ばないままだ。英語の本を日本語訳で読んだとき、文章から受ける印象が違うように、きっと韓国語もじかに読めると抱くものが違うんだろう。
研究対象にしたいアメリカ人作家の先行研究を探していて、鉱脈を見つけた。英語圏に学術書や論文があまりない中、アメリカと日本で注目されたより少し前にフランスで小さな流行りがあった。英語圏のものにせよ、フランスのものにせよ、私が扱いたい近年の作品のものについてではないのだが、大切な先行研究として読むべきだ。
学部時代、第2外国語はフランス語にした。語学の単位を落としたら即留年、同じ学年で2回留年したら退学という決まりだったので、必死で勉強した。「英米文学を専攻するならフラ語でしょう」という空気に流されたゆえの選択だったから、フランス語組と違って学生が少なくて、のんびりしていて、授業後にコリアンレストランへお昼を食べに行くような韓国語組が当時からうらやましかった。上述のように、この数年で韓国文化に興味を持ち始めたこともあって、フランス語の選択をうじうじと後悔して、「あの時韓国語にしておけばよかったなあ。今頃1曲歌えたのに」とよく思っていた。
私が受ける院試は社会人入試で、外国語試験がない。一般入試とて、志望校の英米文学専攻は英語しか選べない。専門試験は英語。「やっぱりフラ語いらなかったじゃん」と思いきや、今になってフランス語の本と論文が見つかった。わからない単語は多いけど、文法は覚えているようで、なんとなく読める。辞書があれば大丈夫そうだ。年を重ねると何が起きるかわからない。
写真を撮ってAIに読ませれば、一瞬で訳が出てきそうな気もするけれど、私は、私の中に眠っているフランス語を起こしてみたい。韓国語も美しいだろうが、フランス語も美しいんだ。演習でランボーの詩集を通読し終えた日、冬の午後、白いカーテンの隙間から射す光、静まりかえる教室、ほほえむ先生。
先月注文しておいた本が、フランスから郵便で届いた。封筒に貼られた長方形の切手が綺麗だ。しばらくは当たり前に英語ざんまい。試験に受かったら、フランス語をやりなおして論文を読む。やることいっぱい。いそがしい。でもきっと大丈夫です、私はまばゆいから。