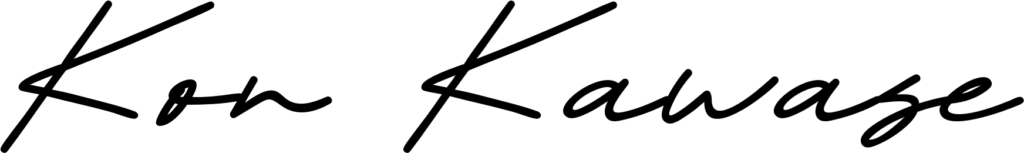New Essays Every Monday
-
コルクがぽんっと抜けたような
学校や会社で関わるすべての人と仲良くなろうとする必要なんてなかったことに、昨日の夜、突然気づいた。同期や同僚という言葉でくくられる以上、よい構成員にならなければと思っていたけど、間違っていた。機嫌を取ったり評価を気にしたり、うまく振る舞えなくて落ち込んだりしなくてよかった。
気が合う人とはそのままでいいし、そうじゃない人とは最低限の関わり以外、何もがんばらなくていい。いやはや。とっても拍子抜け。
-
愚か者
やけに破れている本だと思っていた。古本、岩波文庫赤帯、回想録、上下巻の2冊セット、カバーなし。古本でしか手に入らないもの。英語で1章分の抜粋を読んだあと、通読したくてネットで買った。
「これは私に必要な作品だ」という勘は当たって、どんどん読み進められる。ページの3隅が茶色く焼けているのに加えて、下の方が小さく破れている。高まっていく知的な興奮に、残念な気持ちがちらつく。説明欄に書いておいてほしかったな。でも安かったから仕方ないか。あーあ。
上巻の半分を過ぎたころ。左のページの文章を読み終えて、次のページに行こうとした。少しだけ視線をずらした。私の指がページをぴりっと破いていた。合点がいって、ページの端をそっと触ってみた。またぴりっと破れた。「なんて馬鹿なことを」と吐きつつ、「いや、偶然かもしれない」とも思い、もう一度別のページで試してみた。私じゃん。
「何度も読み返す本になりそう」という予感を強めていたので困った。がしがし読むのに耐えられない。「ええい、売ってしまおう!」と決めて巻末を見たら、初版本だった。「この繊細さは初版でいらっしゃったからなのですね」と思うと売りにくくなった。無邪気な犯行も愚かだが、社会的に価値のある人だとわかって態度を変えるような真似もまた愚かだ。誰かのせいだと疑ったことも恥ずかしい。主人公のまっすぐな生き方は私に、この本を読むのに値する、所有するのに値する人間かと問う。
「日本の古本屋」で別の古本を探す。上下巻セットで、発行年が新しいもの。
背筋を伸ばし、「お取り扱いありがとうございます。誠に恐縮ながら、再度注文いたします。つつしんで拝読する所存でございます。よろしくお願いいたします」と一礼してから決済ボタンを押した。

-
宝物を抱きしめて眠る
長いこと続いていた睡眠障害から回復した。入眠しにくい、途中で起きてしまう、眠れても合計5時間くらいだったのが、入眠スムーズ、中途覚醒なし、7時間半睡眠になった。
布団に入る数時間前から頭のスイッチをオフにし、休む準備をしなければならないとわかったのが大きかった。ぼーっとしながら夕食を消化し、お風呂のお湯がたまる間にストレッチをする、お湯に入浴剤を入れて深呼吸する、を繰り返していたら、自律神経が整ったみたいだ。私は受験までに勉強だけをしたいのではなくて、勉強と運動と休息と家事の習慣をまるごと作りたかったので、ようやく突破口を見つけた感じ。
1日を少しずつ閉じていくときに、スマホもパソコンも見たくなくて、音楽プレーヤーを使うことにした。音と写真とコンピュータ関係は夫に言ってみるもんである。だいたい何かしら持っていて、おさがりをくれる。今は亡きKENWOODのプレーヤーをもらった。Spotifyに入る前に買っていた音楽データを入れた。働き始めたころからコロナ前くらいまでのデータ。なつかしい、お気に入りの曲ばかり。電気を消してイヤフォンで聴く。
落ち着いて勉強できるようになるまでに、適切な休息をとれるようになるまでに、年齢と同じ時間が必要だった。試行錯誤を繰り返して作った習慣たちを抱きしめて眠る。