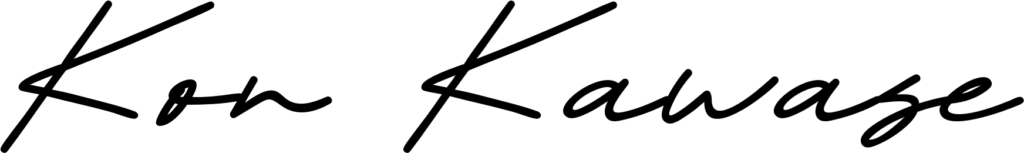New Essays Every Monday
-
菓子折りとスパイ
学籍番号が私のじゃない。大学の教務課に申請した在籍証明書に間違いがあった。通常、証明書の申請には自販機みたいなものがあるのだけど、研修生にはない。研修生の数が、業務を自動化するコストに合わないんだろう。だからたぶん、これは私の前に申請した人の書類を上書きして作ったんだろう。私の情報はそのまま保存されるんだろう。・・・・・・次の人の証明書でまた同じミスが発生するかもしれない?と、ビジネスモードの私が出てくる。この仮説を含めてメールで問い合わせしたら、次の日に電話がかかってきた。「まったくその通りだったので、申し訳ない」「業務の見直しをする」「証明書は再発行するので取りに来てほしい」とのことだった。次の週、2限の授業が終わって窓口に向かう。お昼休み中で人が少ない。奥のホワイトボードに1日のスケジュールとタスクが書き出されているのが目に入る。用件を伝えると場の空気が少し張った。残っていた方々が小声で話し合い、あっちへ行き、こっちへ行き、おひとりが私のところへやって来た。「このたびは本当にお手数をおかけしました。教務課長もお詫びを申し上げようとお会いしたがっていたのですが、あいにく退席しており・・・・・・」と言われる。「菓子折りをいただけるなら待ちましょうか」と返したら、爆笑されて場がほぐれた。人間、ミスはあります。ありがとうございます。
研修生として、初めての学期が終わった。指導教官に個別指導の時間をいただく。とても充実していたので、やはり何年か続けたい、計画を立てたいと申し出る。「次回のセッションで考えましょう」と言われる。15時半から始まったセッションを終えたのは18時過ぎで、外はすっかり暗くなっていた。オレンジの光がぽつぽつ灯るキャンパスに、風に揺れてしゃらしゃらと鳴る木々。金木犀の匂い。私はここに、あとどれくらいいられるだろう。先生と計画を立てるなら、制度の制約も知っておきたいと思い、翌朝、自宅から教務課に電話する。数年に渡ってこの制度を使い続けることは、指導教官の許可があれば、大学的には大丈夫なんでしょうか。たとえば5年くらい、毎年継続申請したとして、その長さゆえに、スパイかな?とか、変な学生だなとみなされて不合格になることはあるんでしょうか、と尋ねる。私は「利用限度があります」と言われる可能性を見越して緊張し、真面目に尋ねていたので、「はっはっはっ」と電話口で笑われて、つられて笑った。「学科は申し上げられませんが、コロナ前から使ってくださっている方は複数いらっしゃいますよ。だから大丈夫です。使い続けていただけるとうれしいです」と言われた。
研修生は、正規生に比べると費用が抑えられる。他の大学ではもっと高額で、かつ聴講のみ、個別指導なし、というところが多いのに、この大学は違う。指導教官によっても大きく違うと思うけれども、私はたいへんのびのび、ふくふく栄養をいただき、頭をフル回転させて生きることができている。永遠に続くものはない。寒くなってぎゅっとこわばる体。ありがたみを噛みしめる奥歯。
-
25m潜水、クイックターンでもう25m
澄んだ水面が小刻みに揺れる。清潔に管理された匂い。足を浸して、プールのふちに座る。そういえば、「あなたはどう思いますか」と問われることが増えた。あなたはどんな人? あなたの考えはどんなもの? その背景には何があるの?
大学で今学期取っているのは英詩の授業で、毎回アクティビティーシートといくつかの詩が配られる。詩をあらかじめ読み、アクティビティーシートにある7つほどの問いに自分の考えを書いておくのが宿題。英語でおこなわれる授業だから、英語でまとめておく。「あなたはこの詩の○○について、ポジティブ、ネガティブ、どちらの印象をもちましたか。それはなぜですか」「XXという単語は何を意味していると思いますか。その根拠は何ですか」
オンラインのクリエイティブライティングの授業。説明しすぎの文章はよくないのだけど、私の文章は説明しなさすぎ、明示しなさすぎの傾向があり、先生を混乱させてしまいがちだ。「紺、あなたはこれで何を言いたかったの?」と問われて、あーまたやってしまったと猛省しつつ、書きたかったことをぽつぽつと話す。彼女はそれを受けて、「それはどういう意図なの?」「今言ってた△△という言葉について詳しく教えて」と問いかけてくれる。それでようやく、ああそうかと気づくことがある。自分の中に潜る、それを彼女が待つ、静かな時間。
編み物教室には隔週の日曜日に行っている。他の曜日と違って生徒が来ず、いつも先生とマンツーマンだ。彼女はおしゃべりが好きなので、よく話しかけてくる。編むのが難しいパートにいるとき、私が「先生、ちょっと黙っててください。カウントが飛びます」とお願いすると、「えー、つまんない」とふざけた台詞が返ってくる。そして遅めの昼食やおやつを食べたり、編み物の本を読み始めたりする。他の曜日は数人の生徒がいて、なんだかんだ指導という名のおしゃべりが止まらないから、ほんとうにつまらなさそうだ。でも、私は編み物を習いに来ているのでこれでよい。単純な編み方のパートに入れば、気を緩められる。先生が待ってましたとばかりに話し始める。私は相づちしながら、編みながら、聴く。たまに、流れで私も話す。すると、「え、あなたそのときどう思ったの?」などと問われる。手元を見ながら、考えて、答える。
1回目の大学生時代、授業で当てられることはもちろんあった。だけど正解を言わなきゃという気持ちが強くて、順番が終わると心底安心していた。会社でもそう。何かを問われるということは、往々にして指摘であり、プレッシャーを感じて緊張していた。たぶん私も変わったし、環境も変わった。心理的な安全を感じられる場所で、コンフォートゾーンから半身を出すように暮らしている。問われて初めて気づく切り口。あなたは何を考えてる? 話していいよ。あなたの世界を広げていい。
息を止めて、温水プールを潜水するのが好きだ。泳ぎ切って、ゆっくりと浮いて、ぷはっと息を吐く。ゴーグルで視界が灰色のまま、また潜りに行く。クラゲもいない、サメもいないプールで、深く潜る。
-
ファミチキで測る
夫が風邪を引いた。一度引くとこじらせてしまいやすい人だ。
10月のなかば、金曜日、週末の映画のチケットを買った。そのあと、ふたりとも喉が痛くなった。葛根湯とビタミンを摂り、安静にしておく。映画に行けるかしら、どうかしらと思っていたら、彼の風邪だけ悪化した。私だけ回復するのは悪いことをしているみたいでうしろめたい。
もともと体温が高めの人なので、いつも寒くなるぎりぎりまで夏服を着ている。扇風機も回し続けている。そのせいじゃん。私は秋冬用のルームウェアをクローゼットから引っ張り出してきて彼に着せる。白いトレーナーを頭にぱふっとかぶせた時に、彼は「ぱふっ」と言った。おいおい、余裕だな。例年通りならこれから熱が上がるぞ。
彼は病院に行くと気持ちが悪くなるくらい病院が嫌いなので、布団にくるまって過ごす。我が家では、ウイルスにモテモテの状態を「人気者」と呼ぶ。瞬く間に、どんどん人気者になっていく。はちみつに大根を浸して作ったシロップをお湯に溶かして飲ませる。おいしくなさそうなので私は飲んだことがない。おばあちゃんの知恵袋的によく効くらしく、彼には積極的に勧める。とても微妙な顔をしながら飲みきっていた。人として私より上。
ポカリスエットの大きなペットボトルを買ってきたり、ほうれん草とエビと卵のおじやを作ったりして看病する。熱を測る。高い。声をかけても、頭を縦か横に動かすだけだ。ずっと観たかった映画だったけど、もうどうでもいい。早くよくなるように祈る。連休が明けて、平日が始まってもまだつらそうだった。横になりっぱなしの腰や背中をマッサージする。
私が大学に行く日も、彼は会社を休むことにした。何を食べたいか聞いても返事がない。帰りにハンバーガー屋さんに寄れるけど、何もいらない?と聞く。ようやく「照り焼きチキンバーガー」と返ってきた。食べたいものが出てくるのはいい兆候。でもいつもはハンバーガーふたつとポテトを所望するので、本調子ではない。温かいうちに食べてもらおうと急いで帰って渡したら、はむはむと食べていた。ハンバーガーの白い包み紙に顔が隠れるのは、元気なときだろうがそうでなかろうがかわいい。
次の日、食材の買い出しに行く。買ってきてほしいものを聞いてもリクエストがない。風邪ではないけれど、私も体調が悪くてだるだるしていた。栄養のありそうなものを買って帰った。ベッドに寝ている彼の顔をのぞきこみ、夕食のメニューを伝える。ねえ、ファミチキとか食べたくない?買ってこようか?と聞くと、彼は目をつぶったまま頭を横に振った。そっか、買ってきたんだけど食べないんだね、スパイシーなやつ、と言ったら、目がぱちっと開いて、輝いた。うそですと言ったら、しょんぼりしていた。回復は近い。
熱が下がり、食欲も戻って来たころ。頭はどう?と聞いたら、彼は「いい」と言った。そうだね、きみはいつも頭いいよね。胸が苦しかったりしない?痛みがあるなら病院に行かないといけないんじゃないかなとたずねたら、両手で胸を押さえて「きゅん」と言った。おかえり。