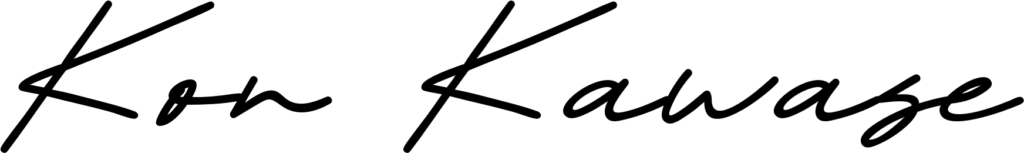New Essays Every Monday
更新情報+αが届くニュースレターはこちら
-
布団から抜け出して、本棚へ駆ける
何にもつよい興味をもたないことは
不幸なことだ
ただ自らの内部を
目を閉じて のぞきこんでいる。何にも興味をもたなかったきみが
ある日
ゴヤのファースト・ネームが知りたくて
隣の部屋まで駆けていた。(中略)
生きるとは
飯島耕一 「ゴヤのファースト・ネームは」から抜粋
ゴヤのファースト・ネームを
知りたいと思うことだ。
ゴヤのロス・カプリチョスや
「聾の家」を
見たいと思うことだ。
見ることを拒否する病から
一歩一歩 癒えて行く、
この感覚だ。
(何だかサフラン入りの
サフラン色した皿なんかが眼にうつって……)
その入り口に ゴヤの
ファーストネームがあった。これは、鬱病を患っていた詩人が回復期に書いた詩。寝込んでいたところ、ふっと、「あれ、ゴヤのファースト・ネームって何だっけ?」と思う。ああ、えーっと、何だっけ、えーっと、と考えあぐねる。布団に寝ていられなくなって、隣の部屋にある本棚へ急ぐ。愛読書、あるいはめったに開かない厚い百科事典を開くなどして、ゴヤを探す。そんな情景を想像した。
元気が出ない時に現れる小さな知的好奇心は、夜空、雲のあいだから見える北極星みたいだ。ずっと待っていた。たかだか他人の名前ひとつでも、あ、知りたいと思えたことがうれしい。布団から出なきゃ出なきゃという切迫感で頭がいっぱいだったのに、気づけば体が出てしまっている。ファースト・ネームがわかったら、次は画集を見たくなる。好きな作品の描かれた年に、ゴヤは何をしていたんだっけ。この絵の、この色合いは、あれやこれやに似ているな。スペインの風景を想像し始める。私だったらパエリアが食べたくなる。世界が広がる、ふくらむ。
私の知的好奇心への欲求は、仕事で忙しくて、でも勉強したくて、という時期にはあまり切実ではなかった。頭と体は動いていて、与えられた仕事で知的好奇心っぽいものを満たせていた。内臓の病気で臥せたとき、頭も体も動かせなくて、何も考えられなくなった。読みたいものはおろか、食べたいものも取り込めない。暇つぶしの音楽にも動画にも、感覚を開けていられない。私は疲れて、諦めて、閉じていった。
時間がとても流れた。布団の中で、急に「括弧は英語で何と言うんだっけ」と思った。ベッド横のワゴンに入った電子辞書に手を伸ばす。届かなくて、起き上がる。和英辞書には、parentheses。英和辞書には、こんなことも書いてあった。「本文とは文法的関係がないが、注釈として挿入された語句」。頭の中で光が走った気がした。飯島にとってのゴヤのファースト・ネームも、私にとっての括弧も、寝てばかりの生活に、ふいに入り込んできた小さな挿入句だった。
回復の途中で少し感覚が開くようになると、世界は穏やかな隙間風のように私たちの中に入ってきて、あれやこれやとつながり、知的好奇心を刺激する。知的好奇心に促されて、体は動き、世界が広がり、ふくらむ。世界を追いかけて、私たちは駆ける。ゆっくり、おのおののスピードで。
-
ベンジャミン・フランクリンさん
ノートンアンソロジーは、大きな時代説明のあと、個別の作家の説明と、重要な作品の全文あるいは抜粋を載せている本だ。英米文学専攻で大学院に入りたくて、今はアメリカ文学のものを読んでいて、次はイギリス文学のものを読む予定。
あまり理解されないと思うけれど、私はこのノートンアンソロジーが大好きだ。文学史的に重要なことはもちろん載っているんだけど、加えて些細なエピソードが散りばめられているのがいい。一般的な文学史の教科書に「有名な牧師」と書いてあるような人の説明で、ノートンは「代々宗教家という家系のプレッシャーで、不安や抑うつがひどかった」などと書いてある。感情移入して覚えてしまう。その人のパートを読み終えたら、「さん」づけで呼びたくなる。
先週はベンジャミン・フランクリンについて読んだ。彼はアメリカ建国の立役者のひとりとして、また自伝や発明で有名な人。加えて、奴隷制度や、私生児を生んだ場合、女性だけが処罰の対象だったことなどに反対した人。一般的な文学史の本の説明はここまで。ノートンには、自伝はもちろん、抗議の文章自体も掲載されていて、より多面的にその人に会える。ああ、こういう点に着目したのか、とか、こういう口調だったのか、とか、この文脈ね、とか。勉強という感じがしない。
ベンジャミン・フランクリンさんと言えるようになって、ノートにメモを残す。この蓄積で、私はどんな世界に行けるんだろう。
-
変わらない風景の水面下
最近、部屋や机の写真を撮ってXに上げることが好きだ。院に行きたいと決めてから、勉強を中心に生活が回っており、早寝早起き、お酒控えめ、ごはんは名もなきものをさくっと済ませる。読みたいものはアンソロジーにまとまっているので、いわゆる本を読んでない。映画も観てない。外出はもともと少ないし、カフェより家のほうが空間的にも飲食的にも落ち着く。だから部屋と机以外の写真があんまりない。
変わり映えしない風景なのに、確実に季節は過ぎていく。アンソロジーと単語帳の読了ページは増え、英文解釈と英作文の使用済みノートも増えていく。ここにある大切なものを残したくて、写真に撮って、言葉を絞り出して記録する。あとから振り返ってどんなことを感じるのか、楽しみにしている。