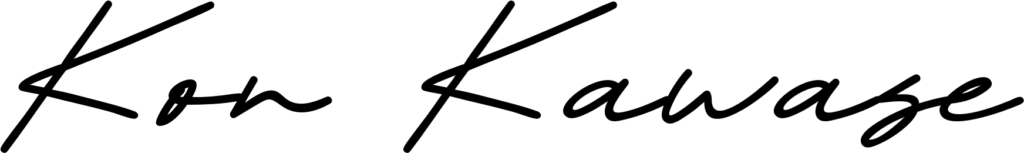New Essays Every Monday
-
9月5週目~10月1週目の日記
9月25日(月)
病院以外の予定をすべてキャンセル。疲れを感じるはずなのに感じないときは、センサーがバグっていて、めちゃくちゃ疲れているサイン。昔はこれがわからなくて動き続け、イライラして夫に当たったりしていた。しーんと静かに見えていた人がいきなり爆発するなんて、いい迷惑である。今の私はここで止まれる。関係者との連絡を終えて、椅子に深く座り込んだとき、ぶわーっと肩の荷が下りる感覚があった。9月26日(火)
メンクリ。通っているのは、3分診療ではなく、先生との時間が1時間とってもらえるクリニック。今日は「Spotifyの速度調節機能がいいんですよー」という話をした。先生が「何それ、教えて。アドレス送って」と食いつく。「先生愛用のNetflixにも同じ機能がありますよ、ほら」と、スマホのアプリを見せながら話した。これは診察?と思うけれど、定期的に会って、調子のいいときは気軽に話し、悪いときは相談できるのが心強い。その足で矯正歯科へ。隣で1歳過ぎらしい男の子が泣きわめいていた。「あの歳でも矯正できるんですか」と歯科衛生士さんに尋ねたら、「矯正してるのはお母さんのほうです。あの子はお母さんのお腹に乗ってるだけです」と教えてくれた。男の子は、お母さんとの接触面積が減っただけで、この世の終わりかのように泣く。スタッフさんは周りで笑ったり、雑談したりしている。カオスっぷりがおもしろくて、衛生士さんとふたりで笑った。9月27日(水)
片付けの日。手術から帰宅後、ほったらかしにしていたスーツケースの荷を解く。秋冬用のシーツを洗って干す。家じゅうに掃除機をかける。お役所系の郵送物を確認済みボックスに移す。ハンディクイックルワイパーでほこりをとる。ひととおり終えた3時頃、ファミリーマートへ。スイートポテトクレープ、鶏の軟骨唐揚げ、ビールを買う。まずはクレープを食べた。ほんとはクレープアイスがよかったんだけど、なかったので仕方ない。クレープを食べるの、いつぶりかな。それから唐揚げを電子レンジのグリル機能でカリッとさせる。ビールと一緒に台所で食べる。ゆずが入っていて驚いた。ほろよいな感じで、野菜の下ごしらえ、アイロンがけを済ませた。9月28日(木)
名駅の高島屋へ。食材を買ってレジエリアに行ったら、今ついたばかりなのに、他の人は並んでいないのに、空いたレジに客を通す係の人に「お待たせして申し訳ありません」と謝られた。ほんの数秒で奥のレジが空き、歩き始めたところ、「ご足労おかけして申し訳ありません」と言われた。手前のレジでも奥のレジでも、買ったものを袋に入れるエリアまではどのみち歩かねばならず、変わらないのに。袋詰めを終えて、別コーナーの、デザートビネガー売り場に行った。年配の女性がレジにいる。お酢を見ていたら、丁寧な口調で試飲を勧められた。「飲んだことがあるので味は知っています。大丈夫です。念のため飲み方の確認なんですけど、はちみつを入れて割らなくても大丈夫でしたよね」と言ったら、気さくな口調に変わった。お会計で謝られる。「賞味期限は2024年の2月までなの。ごめんね」「ポイントカードは持ってる?あ、そう、持ってない。ごめんね、一応訊かないといけなくて」「ちょっと重いけど大丈夫かしら。その袋に入る?ごめんね」。何度も些細なことで謝られ、なんだか楽しくなった。フロア総出のコントかと思った。9月29日(金)
旺文社の『でる順パス単 英検1級 5訂版』を覚えきったので、mikanというアプリでテスト。休憩を挟みながら1日中やった。「完璧に覚えた」が100パーセントに至った。2年前に買って、うまく頭に入らなくて、今年になって勉強法を変えた。やり方って大事。次は4訂版に行く。実は最新の本よりも、昔のバージョンのほうが難しめ。5訂版の地固めをしつつ、新しいものを覚えていく作戦。9月30日(土)
National Theatre Live at homeというサービスのサブスクを始めた。イギリスのナショナル・シアターで上演された舞台を、世界中のどこからでも観れるサービス。字幕が英語だけなので、「私の英語力で理解できるだろうか」と悩んで躊躇していたところ、夫に背中を押された次第。おそるおそる「フランケンシュタイン」を観た。ベネディクト・カンバーバッチが怪物役のバージョン。原作は読んだことがあって、あらすじは頭に入っている。フランケンシュタイン博士に作られた生き物が、生まれて、生の喜びを体感するところから、怪物だと忌み嫌われるところ、言葉を覚えるところ、欲望をもつところ、復讐に走るところまで、原作を少し取捨選択しながら構成されている。英語が理解できた。聞き取れた! 生き物が盲目の老人に教わって言葉を覚えていく姿に自分を重ねた。私の英語学習の目的は、海外の文芸作品、演劇作品を理解して、人生を豊かなものにすること。今年はそれが叶い始めていて嬉しい。10月1日(日)
今月から、バレットジャーナルを新しいフォーマットにした。製造業にいたときのくせで、あらかじめしっかり仕組みを設計しておいたうえで、あとは自動で動くようにする、みたいなことは好きだ。私はタスクを書いたノートを閉じると、何をすべきかさっぱり忘れてしまう。そしてそういう性質であることを忘れやすく、「なんで今日はこんなにやる気がないんだろう」とか落ち込み始める。ノートを開きさえすれば、やることは書いてあるのに。今月からはタスクをもっと細分化して、自分が反射的に動けるようにした。うまくいくかはわからないけれど、うまくいかなければまた改善すればいい。
-
棒読みロマンティック
私「月が綺麗だね」
夫「紺ちゃんのほうが綺麗だよ」
綺麗なものを見たときの会話文として、あらかじめ彼の頭に登録してあるものだ。我が家の決まり。彼は褒め言葉の語彙が少ない。いい、おいしい、すき、すごい、かわいい、以上。言葉じゃないもので感情表現する人だと気づくまでは、たくさんけんかした。今なら、出したピザが一瞬で消えることがどんな言葉よりも雄弁だとわかる。ただ、こちらとしては、普段と違った感じのお酒やお花を用意して、おしゃれもして、彼の帰宅を待っていたのである。たいした会話もなくピザに集中されると切ない。
月を見るとき、彼はオタクっぷりを発揮することが多い。お気に入りの単眼鏡を取り出して、ピントを合わせ、「ほーら見てごらん」と私に言う。たぶん彼の思考としては、「好きな人と月を見る」→「それならしっかり月面が見えなくちゃ」→「スペックのいい単眼鏡を選ばなくちゃ」→「よーし今が使いどき。一緒に見るぞ」なんだけど、一緒に月を見るというのはそういうことじゃなくて、いや、そういうことがあってもいいんだけどそのまえに、なんか雰囲気を作って楽しむものだと思う。
ということで、私が「綺麗」という言葉を使ったら「紺ちゃんのほうが綺麗だよ」と返しましょうという約束をした。私が憧れていた、気の利いた台詞だ。具体的・技術的なところに行くまえに、隣の私に意識を向けよとの要請である。年季が入り、彼は今や憎たらしく棒読みで言う。いわゆるロマンティックな雰囲気とはちょっと違う。ふたりでけらけら笑ってしまう。これはこれでいい。
中秋の名月の日。満月になる時刻に、私は自分の部屋の窓を開けて月を見ていた。彼がタイミングよく帰ってくる姿が見えた。配置的には「ロミオとジュリエット」だけど、まあそんなやりとりは期待しない。夕飯前、一緒に月を見た。「綺麗だねー」と言ったら、彼はいつも通り、定型文を棒読みした。
-
私にとってはすべてがギリシャ語
be all Greek to me
直訳:私にとってすべてがギリシャ語である
意味:ちんぷんかんぷんであるリスニングの勉強に、「クリミナル・マインド」を見始めた。FBIの話。昔見たときは、勉強の意識なく、英語音声と日本語字幕だった。今回は英語音声と英語字幕。
6割くらいは難なくわかる。2割は巻き戻すなどしてがんばればわかる。残りの2割はわからない。主要人物の発音は明瞭で聞き取りやすい。だけど、緊迫した雰囲気で犯人のプロファイルを分析するシーンなどが、とても速い。リード氏については専門用語の列挙を1.3倍速で話す。字幕を見てもちんぷんかんぷんである。
何がちんぷんかんぷんなのか、要素を特定するのは大切だ。特定できれば対策が打てる。訓練の計画を立てて実行できる。そういうことが、大学時代よりずっとうまくなった気がする。1日1エピソードを目標に、スピードに慣れたいと思う。