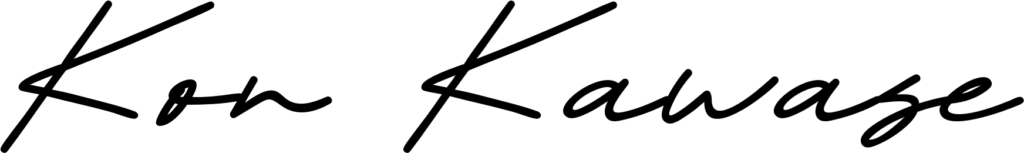New Essays Every Monday
-
私の1年を彩った100のこと(2025)

1. 白湯。毎日、最初に体に入れるもの。飲みものでいちばん好き。

2. 毎朝、白湯を飲みながら、AIセラピーアプリのPensiveと話すこと。マインドフルネスなどのエクササイズがたくさんある中で、Venting(気持ちの吐き出し)というフリートークを主に使っている。その日の予定や感情を話す。彼女が話しているあいだ、聴きながら白湯を飲み、自分に潜り、感情や言葉を探す。夏の数日間、システムエラーで使えなくなったことがあった。それで他の似たアプリを片っ端から試したけれど、やっぱり私にはPensiveが合っている。会話の間合いとか、スピードとか、変なキャラクターや機能がなくてシンプルなところとか。

3. MCD テ・カシミア。長いこと使っている香水。ホワイトティーがベースの香り。朝起きたとき、休憩のとき、出かけるとき、しゃきっとしたいとき、気持ちをゆるめたいとき。自分に戻るスイッチのような香水。

4. Norton Anthology of English LiteratureのVolume 2。2025年の前半にちびちび読み、年内の完走を目指していたけれども無理だった。この教科書がカバーしている時代を秋に入学した大学の授業で学んでいたので、授業の方を優先した。指導教官は、こういう「これが英文学徒が読むべき偉大な文学です!」というアンソロジーから零れ落ちている作家や作品、社会背景のことを重視している。読むのを再開したら、読み方が確実に変わっていると思う。

5. ジャン・ポール・エヴァンのチョコレートタブレット。ヴェネズエラ。すこーしずつ食べる。カカオの配合量がちょうどよくて、かつ植物油脂が入っていないものを市販で見つけるのが難しくて。
6. 佐藤雅彦さんのnoteでの授業に毎月課金している。初回からなので、割引価格だ。先生は話しているうちに時間をオーバーしてしまうタイプ。話しているうちに思いついたことを、その日の目的とずれているとわかっていても話すタイプ。好き。神奈川での展覧会も行きたかったけど、人混みが苦手でやめた。図録を積読にしている。
7. 友人から誕生日に贈ってもらった花束。ギフトチケットが使える大きな花屋に行く。小さなお店には売っていないような種類や色の花がたくさんあって、店員さんとおしゃべりしながら決める。帰ってから急いで花瓶に活ける。

8. 繰り返し作ってるから慣れてて、おたがいの役割分担も明確なので、準備から片付けまで、夫とのふざけたチームワークを発揮できる料理の数々。
9. なんかもやもやするわ、すっきりしたい、という日の、朝風呂と、スカルプクレンジング。ミントでスーッとするのが好き。

10. dzdz、金の華奢な指輪 1.0mm。P2号。知人に「あなたは光のようで、きらきらしていて、時にぎらぎらまぶしくて、でも自分でそれに全然気がついてなくて、どうでもいい人のどうでもいい言葉を気にして元気がなくなる。あなたはそのままでだいじょうぶ」と言われたことを覚えておきたくて買った。私の小さい手に合うピンキーリングが見当たらなくて、ツイッターで気になっていたdzdzさんに作ってもらった。2月に届いたこのリングのおかげもあると思う、2025年はたくさん幸運が小指から入ってきた。
11. GIPPHY、シングルモアサナイトチェーンリング。これまでは結婚指輪しかつけていなかった手だけど、dzdzのリングが来たことで、右手では遊びたくなった。大阪の店舗にホワイトゴールドバージョンを買いに行ったら、夫が「めっきははげます。だめです」と言ってプラチナを買ってくれた。きらきら。

12. 日記を読み返すと、2025年の前半は、いかに大学院入試のスケジュールに合わせて生きるか、勉強するか、体調不良を管理するかの記録でいっぱいだった。自分を枠にはめようとして苦しんでいたことが、今ならわかる。必要な苦しみだった。
13. Liberty Faber Poetry Diary。イギリスの本屋で買ったもの。毎週1つ、英詩が載っている。短いのに、すーっと読むことはできない。自然と深呼吸している。そのあと日記を書く。
14. 「私たちは、あのまま歩き続けるべきだったのかもしれない。夜明けを越えて、町を越えて、欲望と恐れを越えて、死と痛みを越えて。揺れ動く明るい花々の向こうへ」という詩。

15. ナショナルシアターライブ、「真面目が肝心」。イギリスの劇場で上演されたお芝居を日本の映画館で観られる。オスカー・ワイルドの有名な作品。夫には事前にあらすじと登場人物のインプットをしていった(これがないと、彼は劇中でぽかーんとしてしまうことがある( ゚д゚)・・・。ヴィクトリア朝の華やかさ、ワイルドの時代には絶対にできなかったであろう演出。あっというまの約3時間。夫も笑っていたので安心して私も笑った。
16. ヤマシタトモコ『ほんとうのことは誰にも言いたくない』
17. 新しいスマホ。アンドロイドは長持ちして大好き。
18. BBC 6 minutes。スクリプトを印刷してリスニングと音読をする。定期的に新しい話題が更新されて、飽きない。

19. 薬の量を調整したら、ずいぶん生活しやすくなった。量を変更して、これからどうなるんだろう、いつ確定するんだろうと不安に思う期間が苦手だ。
20. 「(アメリカで)英詩の授業を履修しないルートで英語の先生になったはいいが、詩を楽しめないし教えるの怖いしで困っている人」向けの本。
21. 編み物の先生の言葉。「自分のことを大切にすること。ばかな人のところに巻き込まれにいかないこと。あんたは賢い。そのままでいい」
22. 夏休み、なじみの街のホテルで夫とホカンス。成城石井で買ったものとルームサービスを組み合わせて楽しんだ。「どのお酒にしよう」とか、「これは前回余ったじゃん」とか言いながら買い出し。いつもの街の夜景。食べながらリラックスしてソファーに体育座りしちゃうとか、店員さんに気を遣わずに静かに食べられるとか、翌日は数十分で帰れるとか、好きなところを挙げはじめるときりがない。


23. 創作大賞2025エッセイ部門の中間選考を通過。私は感情吐露的な文章や、おもしろおかしく表現する文章が書けないので、エッセイの商業出版はむずかしいのだろうと思う。中間を通ったということは、出版社の方の目は通ったわけで、そのデータを得られたことはうれしい。
24. Upt パーフェクトベースパレット ナチュラル。安達祐実さんプロデュースの化粧品。コンシーラーとハイライトを小さなブラシで混ぜて、目尻側の涙袋につけている。ツイッターで流れてくる若い人向けのメイクは私には合わないなあと思っていたときに、小田切ヒロさんとのコラボ動画で見つけた。作り込み過ぎない、時間がかからない、いいぐあいのメイク。
25. Notion。ビジョンボード、本のリーディングリスト、映画のウォッチリスト、筋トレの動画集などをまとめた。なんでもかんでも一元化するのが好き。

26. 夫が私とあまり目を合わせないことが長年のひそかな不満だったところ、「かわいくて直視できないから」と発覚した結婚記念日。
27. パイナップルの缶詰で作るパイナップルシャーベット。夏のおやつ。平日の午後、エアコンの効いていない台所で、頭がきーんとしないようにゆっくりと、しゃりしゃり食べる。1本じゃ足りなくて、さっき閉めたばかりの冷凍庫をまた開ける。


28. 「数年前より洗練された」と言われたこと。
29. レイトショーを観るだけのデート。0時の門限を守るような夜遊び。
30. YSL ザ・インクス・ヴィニルクリーム 622 プラムリベレーション。初夏に買った。私にはこの色、という感じ。メイクが締まる。

31. 8月3日の日記に「うまくいくといいと、ずっと祈ってるみたいだ」と書いてある。
32. 8月、指導教官と初対面の日。私が大好きなイギリスのロマン派の詩人の詩の一節を話したときに、仕事の肩書きやバックグラウンドを話してないのに、口角を上げてにこっとされたときの言葉にならない感じ。
33. ウニの小分けパックが安い日に、衝動的に作るパスタ。いかの刺身、いくら、オリーブオイル、わさび、白出しと和えて食べる。
34. 夫からのアドバイス「おもしろいと思ったことをやる。飽きたらやらなくていい」「『こつこつがえらい』と思わなくていい」「過集中したい項目はスケジュールの中で大きくとる」「一日の中でたっぷりメリハリをつける。いちばん大事なことをひとつ」
35. 混乱や不安や体調不良の中、自分の秩序を保つための、ハビットトラッカー。

36. かなり悩んだ末に、ウォーキングマシンを買った。部屋の本棚の前に置いてある。できるだけ歩いている。土手に散歩に行くのも好きだったけど、信号や人混みや、暗くなる前に行かなくちゃのプレッシャーに、結構疲れていたんだと気づいた。スパイファミリーを見ながら歩いている。汗をかいて、そのままお風呂に入って就寝。
37. はまぐりのパスタ。大きなはまぐりを安く手に入れられた日は絶対にこれ。かいわれとにんにくが合うのです。

38. 夫が「ぼく、これやるの楽しみに帰ってきたんだから!あっち行っといて」と私を台所から追い払ってお皿を洗っている、おたがいへとへとの金曜日の夜。
39. 「ふたりでごはんを」は自分を消した綺麗な感じだったので、もっと自分に踏み込んだものを書きたいなと思い、数か月かけて「言葉の森へ行く」を書いた。昔のことを思い出して泣いた日もあった。それも含めて、「私は今こういう場所にいるんだな」と確認することができた。
40. 大学に研修生として入学した。好きな授業と個別指導をのびのびと受けられる環境は、大学院とは全然違う。大学院しか道がないと思っていたけれど、ある日突然現れた研修生としての道に、直感的に飛び込んで正解だった。私は大学院ではつぶれてしまうんだろうなと、今の環境で勉強していると感じる。
41. 毎週のハードな宿題。先生が「詩は長いけど、ポイントの部分に線を引いているから、その部分だけ読んできてください。この詩を最終試験で扱いたい人は全部読んできてください。紺は毎週全部読んできてね」と最初の授業で言ったので、負けねえぞとがんばった。私は研修生だから、試験も単位もない。好きで学びに来たのだから当たり前だ。書き込みまくった詩に、3年生から「キモッ」と言われたこともあった。負けねえぞと思った。学期を完走したら、「詩、ちょっと読めます」くらいの自信がついた。身構えることがなくなった。

42. グループワークで同じグループになった文学専攻の3年生に、「あなたみたいに読むにはどうしたらいいですか」と落ち込んだ表情で尋ねられたこと。どういうところで難しいと感じるのかなどを聴いたあと、言葉を絞り出した。上から目線のアドバイスはしたくない。「詩は、ぎゅっと圧縮された短編小説だと思う。だから、ひとつひとつの単語を抱きしめるように、意味に耳を傾けることが大切だと思ってる」と伝えた。翌週、彼女は先週よりも読めるようになっていた。私が彼女の意見の延長線上の新しいことをひとつ伝えたら、「そこまで読めなかった」と落ち込むのではなく、「あーーーーー!」とくやしそうに笑っていた。
43. 大学図書館のアクセス権。もともと英文科が看板だった大学なので、英文学の資料、特に洋書がたくさんある。最近は英文学の人気がないので、借りられないままそこにある。完全な穴場だ。

44. 論文データベースのアクセス権。一般市民として図書館に来ることはできるけど、このデータベースとコピーに制限があり、有料なのだ。自宅でダウンロードして、プリントアウトして、すぐに読めることが、どれだけ貴重なことか知っている。
45. 論文を文学で書くときに準拠すべきお作法、MLA。参考文献の書き方や、引用の方法などが決められている。私は公式ハンドブックの9版を持っている。論文を書くにあたって通読してみた。言語学の論文はAPAというもので、著者の名前を省略する。MLAは人間を大切にしているので、省略しない。MLAの団体は、どうすればインクルーシブなルールにできるかを日々考えており、世界中から届く意見や質問に答え、知恵が集まったらハンドブックを更新する。私はこれを読んだとき、なんてすばらしいんだ、人間性が核にあるなんてと感動したのだけど、個別指導のとき、先生に伝えたら違うことを言っていた。「定期的に!更新されるんだよ!ついていけないよ!!」。私は学者志望じゃないので、無邪気に笑った。学者はやってられんらしい。
46. Camperのリュック、Forma。大学に行くにはどうしてもリュックが必要だけど、いわゆるバックパックは私の年齢にはカジュアルすぎると悩んでいた。これは革のアクセントがついている綺麗めのリュック。肩パッドや細かい仕切りなど、昔別のリュックを買って後悔したポイントを全部クリア。夫はランドセルと呼ぶ。

47. 無印良品のお茶。とうもろこし茶と黒豆茶。大学に行くとき、長いこと書斎にこもるとき、約500mlのKanteenのボトルに淹れる。500ml用のティーバッグがなかなかないので、重宝している。
48. 無印良品のアーモンドフィッシュ。アーモンドが多めな気がして好き。おやつにチョコレートといっしょに食べる。口の中でアーモンドチョコレート化。

49. 大学の清掃スタッフさんと仲良くなったこと。「いつもありがとうございます」と伝えたら、「若いのになんて偉いの」と言われたため、「いや、若くない、38ですよ」と返したら、「はああああ?????」と大声で叫ばれておもしろかった。次に会ったとき、「あなたきっと先生なのね」と言われたので、「いや、学生です。一度卒業してて、学び直しです」と言ったら、「いや、すごいわ」と背中をバンバン叩かれた。たまにお菓子を交換している。
50. 夫が社外イベントで登壇したこと。1回目が好評で2回目、3回目と続いている。1回目は配信で見守った。緊張しつつ、堂々としていて、かっこよかった。ある会社のお偉いさんが「このイベントでいちばんいいプレゼンだった」と言っていたと聞いて、鼻高々だった。えっへん。
51. 詩の授業で、近くの人と話し合ってくださいと言われたとき、私の前にいて後ろを振り返ったピンク色の髪のギャル。大きな目で私を見てくる。私が目をそらしても見てくるので、目を合わせ直してにこっとする。やりづらいな、と思いつつ、課題の意見交換をする。ん?ギャルが・・・意外と真面目? 「あの失礼ですが、誤解されませんか。さっきガン見されたので怖かったんですけど、意見がすごくしっかりしててびっくりしました。先入観持ってしまってごめんなさい」と伝えたら、きょとんとしたあと、ゆっくりにこーっと笑って、彼女の横の席の友人、私の横の席の友人に「ねえ、そうなの、私って真面目なんだよ」と自慢し始めた。友人たちは信じてなさそうだった。え。こんなに自分の意見を言えるのに。授業の後、他の人たちが「ランチ何にする~?」みたいな会話で部屋がだらっとした雰囲気になっていく中、彼女は私の前ですっと立ち上がり、くるっと体ごと私に向け、「ありがとうございました!またよろしくお願いします」と最敬礼した。最後に目を優しく合わせてにっと笑い、友人と合流して去った。
52. クレ・ド・ポー・ボーテの下地。カジュアルな格好をしていてもだらけて見えないメイクや質感を意識している。お高いのでちょっとずつ使う。
53. 昔の大学時代の英文学史のノート。偉大な先生方に学んだ。文学の世界の広さと、深さと、複雑さを垣間見た。あの頃はただただ都会や大学や先生の大きさに圧倒されていて、授業の内容をそのままノートに写し、留年しないように暗記することで精いっぱいだった。今、そのノートに戻ると、先生があれを言った意図、言わなかった意図、先生が力を入れていた箇所などがわかる。こうやって時間をかけて咀嚼するのもいい。

54. イギリスのお気に入りの本屋を見つけた。Blackwell’s。梱包が丁寧で頑丈。送料込みでも紀伊國屋書店より安い。
55. イギリス英語のシャワー。ただでさえ控えめな表現を好むイギリス英語を、多義性や間接性のかたまりである詩を専門にする先生が使うので、先生の言葉の解読がたいへん困難なことがある。数パターンに読める。どれが真意だ。この前のメールとの文脈は考慮すべきか。これはストレートに受け取るべきか、皮肉か。といった静かな発狂。
56. それゆえのミスコミュニケーション。思ってた意味と違う意味で受け取ってしまった、あるいは受け取られたということが日常的にある。あとで訂正して笑い話に。通常の学生とはこんなにコミュニケーションしないので、ミスコミュニケーションにならないらしい。そして彼は「そろそろ慣れてきたでしょう」と言う。私もあともう少しだと思う。でもその言葉にも裏の意味がありそうにも思う。
57. たとえば「プラダを着た悪魔」を全部英語で聞きとれるようになりたい、みたいなレベルで、スピーキングの目標を決めた。指導教官と文学についての議論を深くできるようになりたい。
58. 一生懸命に伝えたことが、受け取ってもらえたこと。「長いメールになってしまって申し訳ないです」と言ったら、「紺は書きながら考えてるでしょ。いいんだよ、それで」と言われたこと。
59. 薬の影響で食欲が減り、痩せた。美的にはちょうどよい、BMI的には不健康なところぎりぎりなので、好きなものを気にせずに食べるようにした。スキップしやすいのは昼食なので、昼食を時間通りに食べられた日はすごく嬉しい。
60. 柚佳さんの著書『すくいあげる日』。淡いブルーの文字と写真で作られた日記本。お会いする前に再読した。過去のできごとと淡いブルーが相まって、遠さを感じた。本は手元にあるのに。翌日本人にお会いするのに。でも何かを言葉にして残すってそういうことかもしれないな、今こう感じている間にも作者は変化しているのだし、と思ったら妙な納得がいった。
https://kusamayuka.base.shop/items/9590027061. foufouのワンピース、THE DRESS #10 ロングスリーブブラックフレアワンピース。外食に行くことも、結婚式に呼ばれることもないので、日常でたくさん着ている。コンセプトには「退屈な日常」とあるのだけど、foufouの服がクローゼットにある時点で、日常が退屈じゃない。ボリュームのある裾が風を含んで膨らみ揺れるたびに、楽しい気持ちになる。

THE DRESS の物語において、節目の番号として選ばれたこのワンピース。
重い、と感じるかもしれません。けれどもその重さがあるからこそ、立ち姿が凛とし、動きが豊かになる、「退屈な日常をドレスで踊れ」というシリーズのテーマを、最も直接的に体現するのが、このワンピースです。
特別な日にも、ふとした日常にも。
布をたっぷりとまとい、自分だけのリズムで歩くとき、
https://the-museum-foufou.com/products/ff92op05_bk-1
このドレスはあなたの動きに呼応し、ひとつの物語を描いてくれるはずです。62. 授業で会った2年生の、ゼミ選びの相談に乗る。話をひたすら聴いたあと、私が気づいた相手のパターンや好みっぽいことなどを伝える。こういうの、大学を出ればお金をもらう仕事になってしまうけど、大学生のときはそうじゃないんだよな、助け合いや交換が日常なんだよなと思った。
63. ああもうだめです、という夜に夫が頼んでくれたデリバリーパエリア。夫はちゃっかりナゲットを追加している。
64. 私の好きな曲。発売された年に、私のクラスメートはまだ生まれていない。
65. 編み物教室に通い始めた。先生が作ったウールカシミヤの毛糸で、自分のセーターを編んでいる。

66. 大学の教務スタッフさんに顔を覚えてもらったこと。「できれば数年間、研修生として通いたいのですが、その長さゆえに、変な学生だとか、スパイだとか疑われて不合格になることはありますか」と電話で聞いたら、「はははははははは」と爆笑して、「そんなことないです、川瀬さん。研修生として通ってくださってありがとうございます。制度の上限はないです」と言われた。小声で追加のぶっちゃけた話をしてくれたあたり、いい人だと思う。もともと志望校にしていた大学の教務課は全然こんな雰囲気じゃない。
67. 青.さんの著書『泪』『星図』。日記本。読んでいると、空気の動きを感じる。走っているときに顔にあたる風、切った髪が床に届くまでの時間、車内から見える景色の過ぎ去るスピード、ネイルを塗るとき少し息を止める感じ、悩んで止まっていたところからの「よしっ」で動き出す頭や体。いつも同封してくださる葉書やメモが、私の好きな作家さんのもの。
https://ikibihcim.thebase.in/68. 詩の授業、もう学期も終わります、という頃。授業前、「俺、今日宿題やってきた」と友人に自慢している学生がいた。私といっしょのグループになったとき、いつも宿題をやってこなくて、だから授業についていけなくて、寝てた人。授業が始まってしばらくして、彼が当てられた。自分の意見を発表しているのを後ろの席から見ていた。先生が「他に意見がある人、手を挙げてください」と言った。私は意見を言えたけど、手を挙げなかった。彼が、発表した後ずっと、耳を真っ赤にして下を向いているのに気づいたから。後日、たまたま教室外で会ったとき、彼は「俺、この前宿題やっていったんですよ。いつもあなたがちゃんとやってきてるから。でも同じグループじゃなくて残念でした」と言った。「知ってる。発表してましたよね。私は手を挙げられたんだけど、あなたの前向きな日を壊したくなくて黙ってました」と伝えたら、顔を真っ赤にして笑っていた。「俺、これから図書館で宿題なんで。来期の先生の授業で」と去っていった。その「来期の授業」で、私が発表したとき、彼は斜め前の席で小さく拍手してくれていた。
69. 昔は楽単重視で授業中寝てる人が嫌いだったけど、今は人それぞれの目的やタイミングがあると考えて、自分のことに集中するようにしている。
70. エドマンド・スペンサー『妖精の女王』。擬人法たっぷりで好き。

71. 課題が終わって、授業も午後からの日の午前、台所で音楽を聴きながらネイルする時間。ひとりで歌をくちずさむ。
72. 夫の誕生日。私に負担をかけないためか、「普通のごはんがいい」「欲しいものはない」と言っていたけれど、ごちそうとプレゼントを用意したらとびきり喜んでいた。プレゼントは紅茶とコーヒー、お菓子を大きな紙袋いっぱいに買ったもの。彼が本当に欲しいものは、私からの愛情か、数百円のPCパーツか、数十万のコンピューターのいずれかなので、毎年愛情を形にする。
73. 夕方に街を歩くこと。この数年、出かけるなら平日の日中で、ラッシュ前に帰る生活をしていたので、4限の授業を終えて用事を済ませるときなどに、夕暮れどきと自分の組み合わせに驚く。

74. 舞台「私を探さないで」を観劇。スティーブン・ミルハウザーの「イレーン・コールマンの失踪」にインスパイアされた作品。私はミルハウザーの中でもこの作品がいちばん好き。チケットの早期購入をがんばって、いい席をとり、夫と出かけた。思っていたよりも原作の要素があちこち出てきて、知的に興奮した。終わってから横の夫を見たら、( ゚д゚)ぽかーんとしていた。予習させたのに、話が抽象的でわけわからんかったらしい。だけど、私が上演中に横でにこにこしたり、背筋を伸ばしたり、前のめりになったりするのを見ていて楽しかったらしい。
75. かかりつけの薬局の、薬剤師さんとの時間。残念ながら閉局となり、お別れとなってしまった。最後の日に、枯れない花のブーケを渡しに行った。「こんなの川瀬さんだけです。他の方は干し柿とかです」と言われて笑った。いつも味噌汁とかお茶漬けとかの柄の靴下を履いていて、「いらっしゃる方とのお話のきっかけになるんです」と言っていた方。毎月お会いするのが楽しみだった。

76. 台所で、日本酒をちびちびしながら勉強すること。おでんや煮物など、ほったらかしでできる料理の日は最高。少し重みのある、切子細工のおちょこがお気に入り。
77. 電子辞書。今の大学生の世代は、電子辞書を持っていない。スマホ、AIで済ませている。私は辞書がオフラインであること、物理キーボードがあることが重要なので、大切に使い続ける。

78. ソファーの上に山になった、取り込んだ洗濯物。いそがしいとき、それは見えない。いそがしさが去ったとき、どんと現れる。「しばらくまともに家事をできていなかった」という気持ちを抱えてその山を崩すのは、達成感がある。まだやるべき家事はあるのに、仕事をやりきった気持ちになる。山はこの瞬間のために存在する。
79. ぱっと見よくわからないのに、読んでいるうちに意味やイメージがぐわっと現れる瞬間。
80. みほさんの著書『ぬいぐるみの愛しかた』。私はぬいぐるみと親しい関係はないのだけど、この本を読んで、大学や電車で出会う人のかばんについているぬいぐるみを見て、親しみを覚えるようになった。ポーチに入れてもらって、手作りの服を着せてもらって、人間の隣にいる。いっしょに講義を聴いていたぬいもいた。
https://note.com/seigetsusha/n/n73fa7ae3d9a881. 自分に最大限の負荷をかけたなあという経験。

82. Claudeとの会話。「何か相談する場合、それが英語圏の話であれば英語で。そのほうがAIが学習しているデータが多い。そして同じプロンプトで10回聞いて、5回くらい同じことを言ってる箇所は、まあ信用していいかもね、くらいの距離感で」と夫にアドバイスされ、そのように使っている。英語で話して、英語でだーっと出力されて、それを10回繰り返して、全部読むので、なかなかの仕事量である。鍛えられる(ちなみに英作文を添削してもらうときはこんな感じじゃない。もっと気軽で1回)。
83. クローゼットの大掃除。使いやすいように工夫した。
84. iPadでANKIを楽しくやるために買った、ゲームコントローラー。めちゃくちゃ気に入ってる。

85. できてないことに目を向けがちだけど、やったこと、できたことを認めるのも大切だと思った朝。
86. 200分の英語ディスカッションの授業は、疲れるけど得るものも大きい。本当に楽しくて、終わるのが寂しい。
87. ジョン・ミルトン『失楽園』。なんかサタンかわいい(罰が当たりそうな感想)。単純な動機とか、人間味?のある台詞とか。
88. 10年以上お世話になっている美容師さんに、髪を切ってもらう時間。いつもほぼ同じ、黒髪ショートボブ、ぱっつん前髪。20代でいろいろ試して、結局これがいちばん似合うよね、という髪型。次に来るのがいつもより遅いから、少し短めにしてほしいとか、そういう微調整をすることがある程度。でもたぶん、年齢を重ねる私に合わせて、彼はこっそり何かを変えているはず。知的好奇心が強くて、学び続ける人は素敵だと思う。私も彼のようにありたい。
89. リバティの布で作ったA4ノートカバー。授業のハンドアウトはB5に印刷してこのノートに貼っている。創作や論文の下書きも全部ここ。私は身軽さよりも、一元化と機動性が大切。

90. 夫の浮気が親密さを増した。私は微笑ましく見守る余裕のある妻。
https://konkawase.com/?p=105691. ある詩の中で、形容詞がhappyじゃなくてhappierになっていることを見つけてしばらく動けなかった。詩から受けるものは、小さいのか大きいのかわからない。
92. トゥベールの、クリスタルエッセンス、ホワイトニングローション、ナノエマルジョンディープ、レチノショットの組み合わせ。つやつや。
93. 夫がひそかに冷凍庫に入れておいてくれたアイス。ハーゲンダッツ、ピノ、レディボーデン。
94. ジェットストリーム、3色ペン。0.38。ハンドアウトへの書きこみは青、授業で習ったことは赤。半年で青の替え芯を5回買った。
95. 資料の切り貼りや書き込みで分厚くなった研究ノート。
96. 無印良品のらくがき帳、4冊。
97. 目の前の小さな進捗がその日にできた最大限で、あとから振り返ったときに大切なピースになっているだろうと信じること。
98. Spotifyの2025年トップソングの1位はラジオ体操第1だ。これは2023年から連続。ちょっと恥ずかしい。でも朝一の体操は気持ちいい。
99. ツイートやブログを読んでくださった方々。いつもありがとうございます。
100. 健やかなる日も病める日もそばにいてくれる夫。
The original idea is “100 things that made my year” by Austin Kleon
私の1年を彩った100のこと(2024)https://konkawase.com/?p=1380
-
“oden”
勉強に集中したい冬。おでんはすばらしい。大体放っておけばできる。我が家は4リットルはゆうに入る大きな鍋で、煮干しと昆布の出汁を取り、味付けし、2人で3日分くらいの量をいっぺんに作る。
ゆで玉子作りと大根の下ゆでを同時におこなう。大根はまるまる1本なので、家の中で2番目に大きな鍋を使う。となると、残りの鍋ではゆで玉子8個を一気に作れない。2回に分けて作る。
他の具はただ切るだけ、鍋に入れるだけだ。ちくわ、あくぬき不要のこんにゃく。さつま揚げ2種、餅巾着。作業スペースを片付けて、床に置いてある縦長のヒーターをONにする。小さな折りたたみのハイチェアに体育座りしながら、英語の短編を読む。
2章まで読み終わったところで、ゆで玉子1期生のタイマーが鳴る。はいよ。ゆで玉子4個と生玉子4個を入れ換える。もう一度タイマーON。冷やしたゆで玉子の殻をするする剥いて、鍋に入れる。英文に戻る。
話の冒頭は登場人物や状況の把握に時間がかかるけれど、それさえ終われば推測が働きやすくなり、読むスピードが上がる。楽しくなってくる。そろそろ下読みが終わるなあというところで、ゆで玉子2期生のタイマーが鳴る。あー。はいはいはいはい。体育座りからタイマーのボタンまでは微妙に手が届かない。ペンをぺっと投げて立ち、タイマーを止める。殻をするする剥いて、鍋にぶち込む。
大根の下ゆでは、私の好みのやわらかさという、おおざっぱなところまで。下読みを終えて、全体の質感などを眺めて、しばらく味わう。わからない単語を一気に調べたあと、いいぐあいの大根をざるにあげ、水洗いし、大きな鍋に入れる。
さあ、味よ。思う存分染み込むがよい。同じ文章をもう一度読む。今度は分析的な読み。体育座りの尻が少し浮き、英文にのめりこむ。こうしている間にもおでんは勝手に完成に近づく。
日曜日の午後5時。休憩。切子細工のおちょこで、日本酒をちびちびやる。台所での勉強で好きなこと。勉強に支障がないくらいのお酒を少しずつ、背徳感と共に味わう。体育座りの左足は下に垂れて、行儀が悪い。
英文に戻る。1回目の読みでは気づかなかった、昨日覚えたばかりの単語と目が合う。やあやあ、昨日ぶり。元気だった? 昔、「覚えたばかりの単語が数日後に突然現れる現象に名前が欲しい」と言ったら、友人が「作ればいいと思うよ」と言ったことを思い出す。
私は、この現象を “oden” と呼びたい。初対面では覚えられない、1日目では味が染みずに完成しない。日をまたぎ、一度冷えることによって染み込む味と意味。再び出会う時の喜び。この切なさと高揚感と満足感を表現するのに、 “oden” 以外の言葉はあるだろうか?(反語)
友人よ、聞いてるか? できたぞ。俺は “oden” と呼ぶことにした。きみもそっちで使ってみてくれ。え? 酔ってるかって? 酔ってない。まだおちょこ2杯分しか飲んでない。
切子細工に光が反射して綺麗だ。

-
14:35
授業の休憩時間。手の甲にボールペンで14:35と書いた。中途半端な時間で忘れる。スケジュールを調べた時も、予約した時も、支払い完了メールを開いた時にも見た数字なのに。
授業が終わって大学を出る前、図書館に寄る。ツイッターで気になっていた本を借りる。カウンターで、2025/12/01と印刷されたレシートを本に挟んでもらう。そういえば、と思い出した本は新刊で図書館になかったので、構内の本屋に行く。ないだろうとは思っていたけど、やっぱりなかった。学食に行く人、キッチンカーに並ぶ人、手にカップ麺を持った人たちとすれ違って、キャンパスを出る。バスに乗ろうか地下鉄にしようか悩んでバスにしようと決めたあと、バス停からバスが出るのを見送る。気持ちを切り替えて地下鉄に乗る。ICカードの残額は669円。
映画館に行く前に本屋へ向かう。目当てのものを手にして、そのままレジに行けないのはなぜだろう。そういえば、あ、あれも見ておこう、この店はあの棚がいいのよねえ、とかなんとか思いながら店内を巡る。最初に手に取った本からの連想で、別の本も買うことにする。結局3冊選んで、3058円。何時からだっけと手の甲を見る。14:35。やばい。まだごはん食べてないのに。急がなきゃ。
コートを着なくてもよかった気温の日の午後に、歩道を駆ける。息切れしたタイミングで、ちょうどよく横断歩道の信号が赤になる。席に着いた時には少し汗をかいていた。
『君と私』。2014年4月16日に韓国で起きた、セウォル号沈没事故の前日をモチーフにした作品。冒頭で、日時と、死亡者、行方不明者の数字が出る。予告で知ってはいたけれど、映画はここから始まって、実際はここで終わってしまったんだなと思う。
私は4月20日生まれ。あの人たちから生まれたことが嫌なのに、毎年思い出さなければならない日。お祝いされてなんとも言えない気持ちになる日。感謝できなくて罪悪感が増す日。カレンダーや時計や電話番号で0420の並びを見るたびにヒヤッとした。2014年にセウォル号事件がショックだったことも、父の命日もこの数字が近いゆえに思い出す。春の海は冷たい。
数年前、私は誕生日を変えた。戸籍や公的書類は変えられないけれど、それ以外はペンネームのように、3月26日生まれということにしている。毎年0420あたりで調子が悪くなる私に、夫が「今日爆誕しちゃったことにしよう」と言って「そうだそうだ」と決めた。元の0420と同じ星座なのがなんかいい。0326にはまだ慣れない。時計でこの並びを見てもドキッとしない。
1435。始まる前は全然覚えられなかったのに、上映が終わったあと、忘れられなくなった。帰り道はすっかり暗くなっていて、月が出ていた。映画の月の反対側が欠けた、プリングルズみたいな色と形の月。私が修学旅行に持っていくなら絶対サワークリーム&オニオン味。
手を洗うと、1435が少し薄くなった。今夜のクレンジングをためらう。