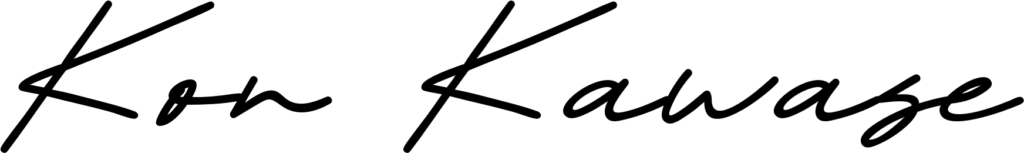New Essays Every Monday
-
ちょろい男
夫と付き合いたてのころ。携帯で写真が送られてきた。部屋の机のパソコン周りの写真。好きな人からの写真なのでよく見た。というか、正直なところ何を返していいのかわからなくて、話のきっかけを探した。
なんかキーボードがきれいだ。なんか私のと違う。なんだ? ああなるほど、ひらがなが印刷されてない。たしか私はそのまま、「キーボードがきれいだね」と送った。それくらいしか言うことがなかった。しかし私はとびきりの正解ボタンを押したのだった。
そのキーボードは、彼こだわりの、US配列のものだった。単にひらがなが印刷されていないだけでなく、Enterキーの感じなど、細かいところが日本語配列のものと違う。エンジニアの彼はUS配列が大好きだった。そこに特に言及することなく送った写真だったのに、私が気づいた。気づいてくれた。とてもうれしくて、きゅーーーんとしたらしい。ちょろい男である。
US配列のキーボードを使っている人を見かけたら、「あ、USなんですね」と声をかけてみるといいと思う。
-
人間が機械になることは避けられないのか
友人「紺ちゃんって、よく人を褒めるよね」
私「昔の仕事柄だよ。2日で100人の顔と名前を覚えて、ちょっとしたことを褒めるようにしてたから」私のファーストキャリアはメーカーの人事の研修担当だった。仕事の基礎も会社のことも知らないのに、新人研修担当になった。夏は事務系総合職よりも長期に渡って開かれている、技術系総合職の研修を見学した。秋、内定者としてリストに上がってきた人たちは、ほぼ年上だった。内定者が100人いたら、80人は技術系で、そのほとんどが修士卒なのだ。私は学部卒の文系。何をすればいいの。
プロフィールを覚えることから始めた。内定者課題のやりとりで、専攻や性格、志向性などを覚えていった。冬、自分で新人研修の準備を始める。研修担当の仕事には大きくふたつある。ひとつは、自分が見つけた問題意識から新しく研修・ワークショップを開発して、自分で講師・ファシリテーターを務めるもの。もうひとつは、大枠の企画だけしてあとは外部の研修会社に任せるというもの。私は前者が得意で好きだった。後者が必要なシーンがあるとはわかっているものの、企画時点から漂う惰性や思考停止感(例:「毎年やってるし、今年も同じで」)が嫌いだった。
私はどういう研修を受けたかったか。私が覚えた100人の新人さんは何を求めているのか。当時の上司は体育会系の人で、ことあるごとに松下幸之助などビジネス界の偉人の言葉を持ち出して研修っぽいものを作っていた。私の同期たちは、先輩たちは、たぶん「会社の大人が言うことってこういうもんだよな」と思いながら聞いていたと思う。私はそれができなくて、「なんでこの人は自分の言葉で話さないんだろう」とイライラしていた。入社式翌日に確定拠出年金の話があった。「入社直後で退職のことを考えさせるって何?」とイライラしていた。どういう言葉で始めて、重要なことは繰り返して、この順番で少しずつ学んで、そのかたわらで過度な緊張を解いてもらって、同期で仲を深めてもらって、という流れの設計、デザインで言うならユーザーエクスペリエンスの視点がなかった。ただ、会社の都合で、それっぽいことを進めていくだけ。人事部に配属後、私がその上司から直接受けた非人間的な扱いが、マイルドなバージョンで新人研究で提供されていたと気づいた。研修で無邪気に笑いあった同期の目は配属から1年後に光を失くしていた。
私は自分の言葉をつかおう。学びの流れを設計しよう。ひとりひとりの名前と顔を覚えて声をかけよう。個々の小さな変化や挑戦を見つけて、伝えよう。
緊張している人。ほとんどが院卒者の中で萎縮しながらも、グループワークでリーダーに立候補する人。「今日も終わったー」と帰る人たちの中で、部屋に忘れ物がないか見回って、見つけたら私に報告してきてくれる人。同じ分野のグループから抜け出して、他分野のグループに話しかけてみる人。日本語がまだまだだけどなんとか伝えようとする人と、それを受け取ろうとして絵やボディランゲージを駆使する人。疲れたり落ち込んだりしている人。週末に髪を切ってきた人。居眠りばかりだったのに、集中できるように生活習慣を整えてきた人。笑顔が増えた人。
見つけたら、休憩時間や研修後に駆け寄って話す。「見てたんですか!?」と驚かれて、一緒に笑う。「川瀬さんは研修ではキリッとしてるのに、それ以外はやさしい。ツンデレですよね」とよくいじられた。
健やかでいてと願うことが、私の仕事の核だと思った。配属後、仕事で何かあったとき、周りの人から人間じゃないように扱われたときのために、「川瀬さんと笑ったなあ」という記憶が残ればいいと思った。リラックマが壁からちらっと顔を出して「みてましたよ。かげながらがんばってますよね」と話すイラストを見たことがあって、そんな仕事がしたかった。研修内容の大半は、受講者の長期的な心身の健康と比べればどうでもいい。そんなこと表では言わないし、うまくやっていたけれど、内心はよい記憶が少しでも残ればいいと思っていた。
人事部は利益を出さない部門に分類される。事業部が稼いだお金を使わせてもらう立場。でもさ、直接的な利益の枠組みを外れたところからできることだってあるんだぜ。効率性を考えれば、実地の研修なんてしなくていい、e-learningにすればいい、100人の名前と顔と性格と魅力を覚えて声をかけるなんてしなくていい、部品のように非人間的に扱って最大限の利益が出るまで使い倒して壊れたら別の部品と交換すればいい。でもそれじゃあ人間性はどこに行くの。その人の健やかさとか、笑顔とか、リラックスしたときに浮かぶアイデアとか、他者への思いやりとか、家に帰ってから料理や趣味を楽しむ余裕とか。
スキル系の研修と違って、やや言葉にならないもの、あるいは言葉にすると陳腐になるものを扱う研修の効果は、「10年後に出ればいい」と言われる。10年経てば正直、効果測定なんてできない。だから、効果があるかわからないけれど何かを願って作る。効果が出ればいいなあ。人によってはすぐ出るかもしれないし、出ないかもしれないし、5年後にいきなり出るかもしれない。個々のペースや性格や可能性を信じる。確実なリターンを求めない。作ったものにリターン=利益を求める部門では集中的にはできない仕事だ。
若さもあって、私はわりと本気で、研修を受けてくれた人たちの健やかな未来を願っていた。4月になると、それをいつも思い出す。
戦時中、僕は爆撃にも耐えられた。しかし、親しい先輩や友人たちが刻々と野蛮に(機械的に)なっていく姿を正視することはできなかった。
渡辺一夫「人間が機械になることは避けられないものであろうか?」p.145 -
かがやくとよいとおもう
だいたい誕生日の2週間くらい前から誕生日の翌日まで、フラッシュバックが強くて体調不良になる。気持ちの上がり下がりが激しいというよりは、なめらかに水中に沈んでいく感じで、いつのまにか体の消化器系が悪くなり、免疫が落ちる。本の文字を追うどころか、うまく座ってすらいられない日々が続く。
誕生日には、ダイヤモンドのピアスを買ってもらった。ブーケをもらった。シャンパンと簡単な料理で夕食にした。いやはや、今年の春はおかげさまで無事に乗り越えられそうなどと夫に話しながら1日を終えた。
翌朝、彼のお弁当だけ作って二度寝した。お昼、「いただきまーす」とLINEが来た。直前まで寝ていたので、自分の昼食に迷う。その意味で「わたしどうしようかな」と返した。「かがやくとよいとおもう」と届いた。
もらったピアスをつけてかがやく。私はそうしているだけでよいのかもしれない。私のかがやきに幽霊がやられてしまえばいい。私はかがやく。