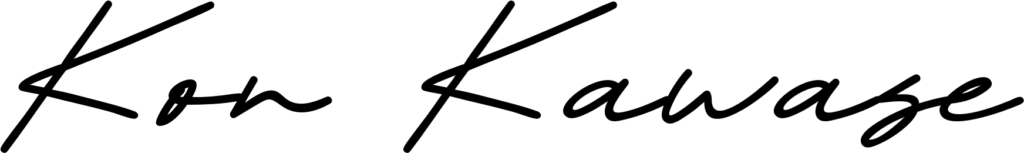「あなたの作品は本当は1位だったんですが、高校生らしくないということで2位になりました。ごめんなさい」
高校3年の秋、電話がかかってきた。夏に受験勉強そっちのけで書いた英文エッセイ。大きめの全国コンクールの審査員からの連絡だった。
私は言葉、英語の話を書いた。どういうところが好きで、どういうふうに遊び、学んでいるかについて、比喩的なイディオムを散りばめて書いた。電話をかけてきた審査員は大学の教授で、私の書いたことが言語学の分野だと教えてくれた。彼としてはどうしても私の作品を1位にしたかったのに、叶わなかったから、せめてもの励ましにと電話してくれたようだった。
「高校生らしいってなんだろう」と思いながら、後日、受賞作がまとめられた冊子を読んだ。いろんな部門の、1位の作品が掲載されている。英文エッセイの高校生部門では、「留学に行って視野が広がった。この経験を活かして社会にとって有益な人になりたい」といった主旨の文章が1位だった。なるほどなるほど。つまらんな。大人たちが好みそうな、優等生像がそこにあった。こういうのをたくさん送る人がいる中で、無邪気な言葉への愛を爆発させた文章に引きつけられ、推す大人がいても不思議ではなかった。不思議ではなかったけれども、そんな大人は絶対に数が少ないと思った。歴史あるコンクールの威厳ある1位には、私の作品はふさわしくない。
私は今、文章を書いて誰に褒められたいのか。それはあのとき「つまらん」と吐き捨てた自分である。彼女が「いいじゃん」と言う文章を書きたい。そして夫。もし私たちが同級生で、同じクラスの友だちだったら、彼は一緒に「つまらん」と言っていただろう人だ。私が何を大切にしているか知っていて、私がうまく表現できるとよろこぶ。ふたりに褒められたくて、私は書いている。