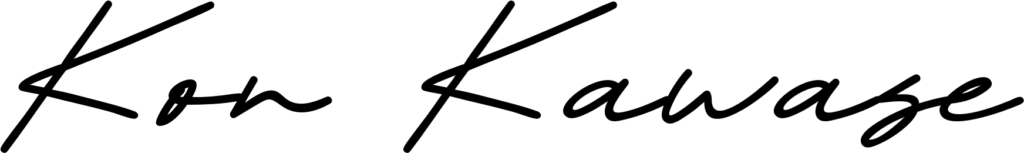照明、追い焚き、換気扇を消して風呂に入ることがある。しばらく湯に浸かり、青い壁を見ていたら、水道の銀色の蛇口の先で、水滴が蛇のようにすっと流れた。暗くて静かなところ、静止画と思っていた視界にいきなり動画が現れて、びくりとした。
シャワーからぬるま湯を出す。頭と手を動かして髪を洗う。泡をふくらませて体を洗う。先ほどと打って変わってせわしない動画。今度は何も見ていない。もう蛇口のことしか考えられない。なんで蛇?
風呂上がり、化粧水の代わりに辞書へ直行した。英語とドイツ語には雄鶏がいた。オランダ語とロシア語には鶴がいて、フランス語とイタリア語には羊が、アジアには龍がいた!スペイン語には、ライオンと鷲の怪物がいた!
アルキメデスを追いかけて、風呂の外で至るユーレカ。おもしろくてにやける。そろそろ服を着よう。
<参考>
各国の「蛇口」を表す言葉。電子辞書 XD-Z9800 内蔵辞書より。
英語:tap、 faucet はいずれも「樽の栓」、cock、stopcock、turncock は「雄鶏」を語義に含む。
ドイツ語:Wasserhahn。wasser = water、hahn = cock。
オランダ語:kraan。crane(鶴)の意味。日本語「カラン」は浴場などの大型の蛇口で、オランダ語から。
ロシア語:кран。読み方は 「クラーン」。オランダ語から来ていて、意味も同じ。
フランス語:robinet の robin が羊。羊の頭の意。
イタリア語:rubinetto。フランス語と同じ。
繁体字中国語(香港、台湾、マカオ):水龍頭。龍や蛇は水神。
簡体字中国語(中国本土、シンガポール):水龙头。龙が龍、头が頭。
スペイン語:grifo。Gryps、ギリシャ神話に出てくる、鷲の頭と翼、ライオンの胴をもつ怪物グリュプスから。