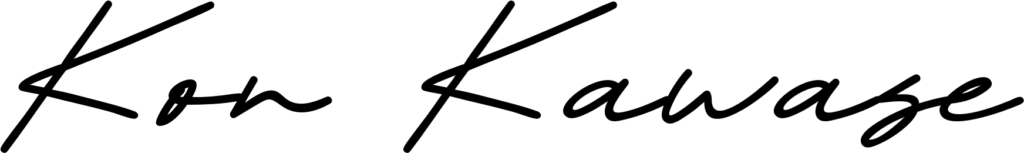使わなくなったポメラを夫にあげた。Linuxを入れて改造しようと、嬉々としている。何をしているのか、その何が楽しいのかはわからないが、ずっと楽しそうなのでこちらまで楽しくなる。何日も、夜遅くまで作業に励んでいた。
シェイクスピアの「マクベス」の舞台が映画館で観られるというので、彼を誘った。平日に行こうという話になり、彼は会社で年休を申請した。申請理由欄には「マクベス」と入力し、教養あるエンジニアを装ったが、原作を読む気はない。
前日、私が主な登場人物とあらすじ、みどころを説明する。彼は目を閉じて、眉間に皺を寄せ、頭を傾けて聞いている。たぶん魔女が出て来るあたりで(それはつまり冒頭部から)理解が追いつかなくなり、マがつく登場人物の数に混乱した。夕飯を食べながら、シェイクスピアの学者と翻訳家による公開記念トークショーを観る。私が「へええ」「なるほど」「あーそういう解釈もねーあるのねー」と食い入るように聴いているのと対照的に、彼はにこにこと私を見つめている。ついてきてない。
映画館の2時間はあっというまだった。限られたキャストが、ひとりで何役もこなす場合があることを伝え忘れていた。「私は白い舞台に影が映えること、透明な壁の使いかた、幼い男の子の演出が好きだった!」という感想で隣を見たら、彼は「英語がわからん、順番が変だったぞ」と言った。そしてひとりで数役こなすつくりを把握しきれてなかった。昼食をとりながら細かく説明したら、初心者にしてはいいぐあいにまあまあわかったようで、満足そうだった。
私たちは別々の部屋をもち、休みの日でもおのおのこもって過ごすことが多い。おはよう、スーパーに行こう、食事をつくろう、食べよう、ちょっとハグしようぜ、掃除しよう、お風呂入れよう、寝る前のごろごろ、おやすみ、くらいしか接点がない。おたがいの研究対象のことがおたがいわからない。研究対象へのエネルギーに共感して生きている。暮らしの中に言葉にならないものがどっさりあり、昔はそれが不満だったけど、今は心地いい。
わかんないけど、わかるよ、あれでしょ。
そうそう、それ。