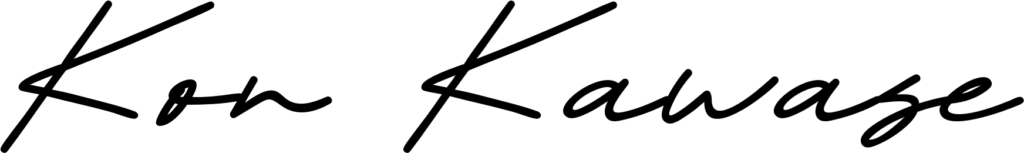寝転がっているときのぎゅうには2種類ある。真摯なぎゅうと怠惰なぎゅうだ。まず夫がベッドに大の字に寝転がる。私が腕に乗る。夫は私が乗っているほうの腕だけ動かして私を抱き寄せる。このぎゅうは怠惰なぎゅうだ。彼は3分もすれば腕の力を抜き、寝てしまうからだ。気持ちのよいベッド、エアコンの涼しい風、横にはかわいい人、ああしあわせ、すぴー。
私は真摯なぎゅうを要求する。真摯なぎゅうとは、背中が完全にベッドにくっついていた状態から体を起こし、体の側面だけベッドに接し、私に向き合って両腕をまわし、しっかりとぎゅうをすることだ。この姿勢は気を抜くと崩れるため、緊張感がある。つまり寝てしまいにくい。私に集中できる。
真摯なぎゅうを要求する 2024-07-22
夫は、薄いすのこベッドにマットレスを敷いて寝ている。休日の昼下がり、私は彼が昼寝しかけているところに乱入した。足をぐいぐい押す。ベッドの端から少しだけスペースを開けてくれたので、私も寝転ぶ。真摯なぎゅうを要求したら、彼はのっそりと体を動かして私に向き合ってくれた。たがいに体をがしっと抱きしめる。扇風機の風が気持ちいい。しばらくして眠気がやってくる。
「そろそろおいとまします」と言うと、彼はここぞとばかりに、「さあ本格的に寝るぞ」と言いたげに、ただちに真摯なぎゅうを終了した。ベッドの端ぎりぎりに寝転がっていた私は落ちた。大きな荷物に結わえていた紐をいきなり切られたように、ごろんと床に落ちた。思いのほか派手に落ちたことがおもしろかったらしく、彼は眠気を吹っ飛ばして笑った。私もつられて笑う。もう1回やってもらう。ぎりぎりのところに寝そべる。真摯にぎゅうする。いきなり手を離される。落ちる。ふたりで再び笑う。再現性のある笑いはいいことだ。
私は奇数が好きだ。2回落ちたので、奇数回、つまり合計3回落ちたくて、同じことをもう1回やった。奇数にしてせいせいしたい気持ちを満たすための行動は、ふたりして事務的になる。はいはい、奇数ね、ぎゅー、ぱっ、ごろん、ははは。
しあわせの沸点が低い。