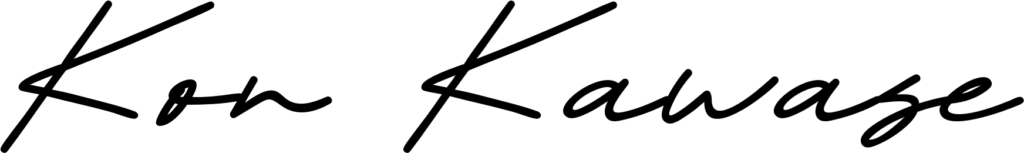エッセイを書いたら夫に見せる。彼はもっている褒め言葉の数が片手で収まるので、大抵は「いい」とだけ言う。「その理由は?」と聞くと「ぼくがかっこいいから」と返ってくることがある。自分が粋な返答をしたとか、創造的な行動をやってのけたとか、存在がまぶしいとかの文章に、彼は(たぶん冗談交じりではあるが)「ふう。ぼく、かっこいいじゃん」と感じるらしい。
彼はSNSをしない。自分からは発信しない。特許情報を除き、インターネット上に彼の直接的な情報はない。かたや私はXを使い、定期的に彼との生活について発信する。彼はそれを嫌だと思っていない。
更新日の月曜日から水曜日あたりまで、よーく観察していると見つかるものがある。エッセイに書いた「かっこいい」言葉や行動の再現性を彼が高めようとする姿である。「言語的コミュニケーションなしに空気を読んで台所仕事をしてくれた」と書けば、「もう1回やって喜ばせちゃお」みたいな、指摘すれば「てへっ」とか効果音が出てきそうな感じの、だからといって自己主張的なわけでもない、絶妙なぐあいの行動を見せる。かわいいひと。
ここに書くことで、誰かに読まれることで、かっこよくてかわいい彼はよりかっこよくてかわいくなっていく。ぐんぐん育ってくれたまえ。