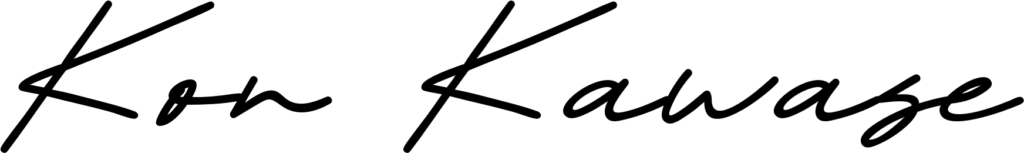読んでいる本に”credit-card terminal”とあったので困った。何。クレジットカードの終点? なんだろう、期限が切れるのかな。なんかすごい絶望的な状態なのかな。でもそういう文脈じゃないし。主人公がいるのはスーパーマーケットだし。
辞書を引いたら、名詞の3番目に「端末」とあった。なるほどねー。ん?なんで終点と端末を同じ単語で言えるの?
ふと思い浮かぶあいつ。あいつは絶対知ってる。あいつは絶対に、「ふっ、そんなことも知らないの?」と挑発的な目を向けてくる。しかし私はあいつが好きだ。仕方ない、聞きに行ってやろう(えらそう)。
私「ねえ、credit-card terminalの意味わかる?」
夫「うん」
私「なに」
夫「端末でしょ。ぴっとするやつ」
私「どうしてterminalなの。終点と端末が同じ単語ってなんなのさ」
夫「システムの末端部にあるのが端末なんだよ」
おお。そうか。カード会社の巨大なシステム。そのいちばん端っこにいる無数の端末たち。
私が苦労して覚えた単語を自慢げに「ねえ、きみ知ってる?」と聞くとき、「うん。○○でしょ」と軽やかに返されることはよくある。どこで覚えたのか聞くと、だいたいコンピュータの用語か、スタートレックか、宇宙で探検したり戦闘したりするゲーム(全部英語)かである。むう。くやしいので、そこに絶対出てこないだろう単語をクイズにして、答えられない顔に「え、知らないの?」と言ってやる。心の狭い私は、人間としての末端にいるような気がしてならない。