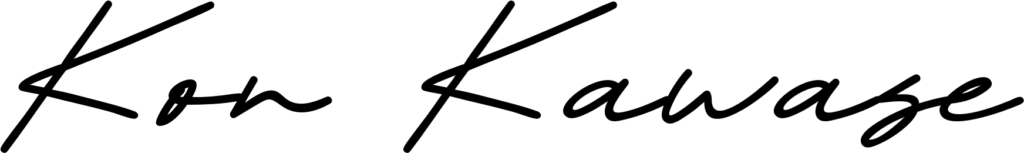スタートレックおたくの夫と、その熱量に引き気味の妻。長年の壁を越える、愛と勇気と成長の記録。2018年夏の自由研究。加筆修正して掲載。
夫はとてもスタートレックが好きだ。中でも「新スタートレック」というシリーズのメインキャラクター、ピカード艦長が大好きだ。ピカード艦長がアールグレイティーを飲むので、彼も毎朝アールグレイティーを飲む。ちょっとした会話の中で、格言めいたものが必要な場合、スタートレックの台詞を引用する。私は「よく覚えてるなあ」と思いながら、話題を変えようとする。スタートレックがこの世に存在するのがうれしいのか、台詞を言えて悦に入っているのか何なのか、話を変えられても楽しそうなままである。
私は食わず嫌いだ。SFって難しそうなのだ。宇宙に技術にエイリアン。それに長そうだ。彼の部屋の棚の上、ドラマのBlu-rayボックスを見るたびに、そんなに観れないよと目をそらす。
ある日、「500ページの夢の束」という映画が公開されるのを知った。スタートレック好きの女の子の話だ。予告を観て、いいタイミングだと思った。一緒に観に行くのを目標にして、スタートレックの勉強をしよう。親しみをもってみよう。スタートレック好きの男の子に近づいてみよう。自分のために、「スタートレックお近づきプログラム」を組んだ。
スタートレックお近づきプログラム 1 刺繍する
1 刺繍する
■クロスステッチ
■トートバッグ
Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
ピカード艦長の部下として、新しい技術開発に挑むエンジニアのためのバッグ。クッション同様、制作時点でピカード艦長がどんな人だか知らないのだけれど、気分は宇宙艦隊、ピカード艦長とエンジニアを見つめる下っ端の小道具担当だった。
2 映像を観る① いいぐあいに親しみを感じてから、いよいよ作品を観る。数シーズンのドラマが、数シリーズある。映画は数本だけど、全部観るには長すぎる。そこで、夫に「厳選ウォッチングリスト」を依頼した。リクエストと返信は次のとおり:
リクエスト
厳選ウォッチングリスト
リストをもらってもなお、「本当におもしろいのか……?」と訝しんでいた人の感想:
・スタートレック:ディスカバリー
映画は、そもそもドラマを観てない人も楽しめるようにつくられている。その中でも、特にこれは!という作品をピックアップ。
・スタートレックII カーンの逆襲
・スタートレックIII ミスター・スポックを探せ!
・スタートレックIV 故郷への長い道
・スタートレックVI 未知の世界
・ジェネレーションズ
・ファーストコンタクト
3 本を読む 100円で入手。キャラクターのおさらい。各民族の特徴、マーク、関係性の学習。映画で観た知識の定着をはかりながら、新しい「へー」を吸収。観てないシリーズのほうが多いものの、映画で足場を固めたことで困惑しなくなった。多くのキャラクターの中でも、初代のスールー、スコッティ、第2シリーズのデータ、ディスカバリーのバーナム、サルー、スタメッツが特に好きだと感じた。ついに推しメンができたのである。
4 バルカンあいさつを練習する スポックをはじめ、バルカン人はあいさつの時、バルカン式あいさつをおこなう。中指と薬指のあいだを開き、てのひらを見せ合い、 “Live long and prosper(長寿と繁栄を)”と言う。作品の外でも、スタートレックの俳優や有名人があいさつや記念撮影でおこなうこともあり、ファンとしては練習しておくべきである。夫はさすが長年のファン、たいへんスムーズにやれる。私は指を開くのに数秒かかるうえに、指先がぷるぷる震える日々が続いた。とはいえ人は成長するのだ。夫へのあいさつをバルカン式でやっていたら、うまくできるようになった。
5 iPhoneを活用する Xの絵文字にしれーっと、バルカンあいさつの手がある。ファンの人がよく使っているようだ。コピーして、iPhoneの辞書に「バルカン」で出るよう登録し、夫とのLINEで使うよう心がけた。ことあるごとに相手の長寿と繁栄を願うのは気持ちいいものである。しばらくして、そもそも「スポック」と打つと絵文字が出てくることに気がついた。Xのみならず、iPhoneにも標準装備だったのだ。無駄に思えるようなところにエネルギーを使えるなんて、なんて知的な仕事をする会社だろう。ネットサーフィンでSiri情報も得たので、確認しておいた。
宇宙艦から惑星に上陸するとき、転送装置が使われる。 “beam me up”は「転送してくれ」、 “energizing”は「転送中」。どちらもよく出てくる言葉。 6 クリンゴン語を学ぶ 戦闘好きなクリンゴン人が使う言葉は、スタートレックオリジナルの言語だ。言語学者が発展させたもので、世界にはクリンゴン話者が一定数いるらしい。Googleでは表示言語で、Bingでは翻訳でクリンゴン語を選べる。使用者がいるということは、教育方法があるということだ。調べると、英語での学習限定だけど、辞書、文法書、オンライン教材があった。PC・スマホOKのduolingoで勉強してみた。項目ごとに細かくレベルが分かれていて公文式みたい。反復練習をしばらくやると、なんとなく、語順と接続詞は判別できるようになった。だけど綴りが難しい。大文字と小文字が区別され、主語と目的語によって動詞が複雑に変化するのも学習の高い壁だ。
例文に、スタートレックのクリンゴン人「ウォーフ」や、「私は私自身を称賛する」「私はあなたを称賛する」「AはBを殺す」「何が欲しい?」といったクリンゴン人らしい内容が出てくるのは楽しい。荒っぽく、自他ともにクリンゴンを褒め称え、戦っている。
duolingoに音声データはないらしい。YouTubeに「ドイツ出身のクリンゴン語の先生」がいらっしゃったので、少しレッスンを受けてみた。
彼によると、クリンゴン語には “Hello” “Thank you” “Goodbye” にあたるものがない。直接的な物言いをする。あいさつっぽい “nugneH” は、”What you want?”、「おまえは何が欲しいんだ」である。発音も独特だ。戦士っぽいハキハキ感、異星人っぽい不思議な感じ。バルカンあいさつのようにとっつきやすいものを探して、 “Qapla’” を覚えた。読み方は「カプラ」、意味は “Success”。大事な戦いの日の朝に使っている。
7 映像を観る② 映画だけでは夫の好きなピカード艦長の人柄をあまり知ることができなかったので、追加のウォッチリストをつくってもらった。映画は基本的に有事で、何かしら緊急事態、ミッション、戦いが起こるものだけど、ドラマはそうでもない。シーズンごとに数十作ある分、宇宙船でのクルーの日常、人柄がゆっくりと描かれている。原題と邦題の違いも興味深い。
・超時空惑星カターン
・ギャラクシー・ロマンス
・運命の分かれ道
8 「500ページの夢の束」を観る 2018年9月7日公開。スタートレックが好きな、自閉症の女の子が主人公。スタートレック脚本コンテストの原稿を書き上げたのに、郵送が間に合わない。直接パラマウント社に届けるべく、長い道のりをひとりで旅する話。詳しくは書けないけれど、予習がばっちり効いて、スタートレックを使った比喩で言おうとしていることが理解できた。映画のあと、焼肉を食べながら、夫とスタートレック絡みのシーンや感想を語り合えた。バルカンあいさつもクリンゴンカプラも出てきて、うれしかった。
VIDEO
以上が、スタートレックに親近感を抱くために私がおこなった策のすべてだ。食わず嫌いからファンになったからこそ言える、SF用語や膨大な作品数など、スタートレックには「難しそう」「楽しくなさそう」といったバイアスを生んでしまう要素がやっぱりある。映画だけ観ても楽しめると知らなければ、ドラマを全部観ないといけないのかと感じる。いくら横で「おもしろいよ!」と言われても、おもしろそうじゃない。技術用語も、軽く流しても話を追えると体験していなければ、いちいち面食らって止まってしまいそうで面倒くさい。ぱっと見違いがわからない宇宙船の「Dタイプがかっこいいよね」と言われても、心が離れる一方だ。
嫌いなニンジンをすりおろして、好きなハンバーグに混ぜ込んで食べてみた。薄く切って、明太子と炒めて食べてみた。みそ汁に入れて食べてみた。酢豚の中のかたまりを、おそるおそる食べてみた。ごま油で炒めるのは好きだけど、バターでソテーするのは嫌い。食べるなら春がいい。最初は全部嫌いだったのに、好き嫌いのレベルが変わった。おたがい、思いのほか楽しめてよかった。
– – – – – – – – – – –
この文章を書いたあと、2024年の追記。
彼の誕生日に、時折スタートレックグッズを贈っている。会社に持って行くアールグレイのタンブラーに合わせてつくったニットカバー。医療班がつけているバッジを刺繍したマスクケース。ピカード艦長役、パトリック・スチュアートの自伝の単行本初版。
トートバッグやクッションは今も現役だ。
私がアメリカ文学専攻で大学院を目指しているのを、彼は応援してくれている。願わくばスタートレックを研究してほしいらしい。リサーチと称して、図書館で延々とスタートレックを観る自分を想像する。む。悪くはない。私が「人間」という単語を使うと、彼はすかさず、「知ってる?宇宙では『人間』って言うと差別になることもあるんだよ」と返してくる。知ってる。きみから何回も聞いたよ。
私が何か頼みごとをして、あるいは何かを一緒に試そうとして、彼がためらうときには、私が「抵抗は無意味よ」とにっこり言う(ボーグが “Resistance is futile.”(抵抗は無意味だ)と無機質に言い放つのに対するオマージュ)。
時は経ち、新しいシーズンやシリーズも増えた。ピカード艦長を主役にした「ピカード」というシリーズを早く観終わりたい。シーズン1だけ、いっしょに観た。年を重ねた艦長が、アールグレイティーを「デカフェで」と頼んだシーンにふたりして興奮した。私はアンドロイドのデータ少佐が大好きだから、途中からずびずび泣いていた。残りのシーズンがもったいなくて、昔の作品から順を追って近づいているところだ。
ディスカバリーでジョージャウ役を務めたミッシェル・ヨーは、2023年、アジア人女性初のアカデミー賞主演女優賞に輝いた。
私がスタートレックを好きになったお返しに、彼は私の好きなカミュの『異邦人』とニザンの『アデン、アラビア』を読んでくれた時期がある。さあ!私も!ついに!彼みたいに!私の好きなものを共有できる!!!どんなところが好みー??!と思っていた。が、願いは叶わなかった。「うん」と言って笑顔で本を返してきただけだった。何を言っているのかさっぱりだったらしい。まあ、読んでくれただけでも、私に近づこうとしてくれただけでもうれしい。
Marriage: one of the frontiers. This is our voyage. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new relationships, to boldly go where no one has gone before.
結婚生活、それはフロンティアのひとつ。これは私たちが、任務を続行して、新世界を探索し、新しい生活と関係を求めて、人類未踏の地に航海する物語である。
使った材料や参照元
1 刺繍するhttps://cloudsfactory.net/star-trek-pillow-sampler.html SWANNY コットンカラーキャンバスhttp://www.swany.jp/shopdetail/000000009354/ Star Trek Font – Star Trek Font Generatorhttps://fontmeme.com/star-trek-font/
3 本を読むhttps://www.amazon.co.jp/dp/4796641602/
4 バルカンあいさつを練習するhttps://www.amazon.co.jp/dp/B01LOXFYDO
6 クリンゴン語を学ぶhttps://www.duolingo.com/ Klingon Course 1: nuqneH & Qapla’https://www.youtube.com/watch?v=auqS6FR_RDE
2&7 映像を観るhttps://www.netflix.com/ https://www.amazon.co.jp/ https://cloud.email.paramountplus.com/Japan
8 「500ページの夢の束」を観るhttp://500page-yume.com/